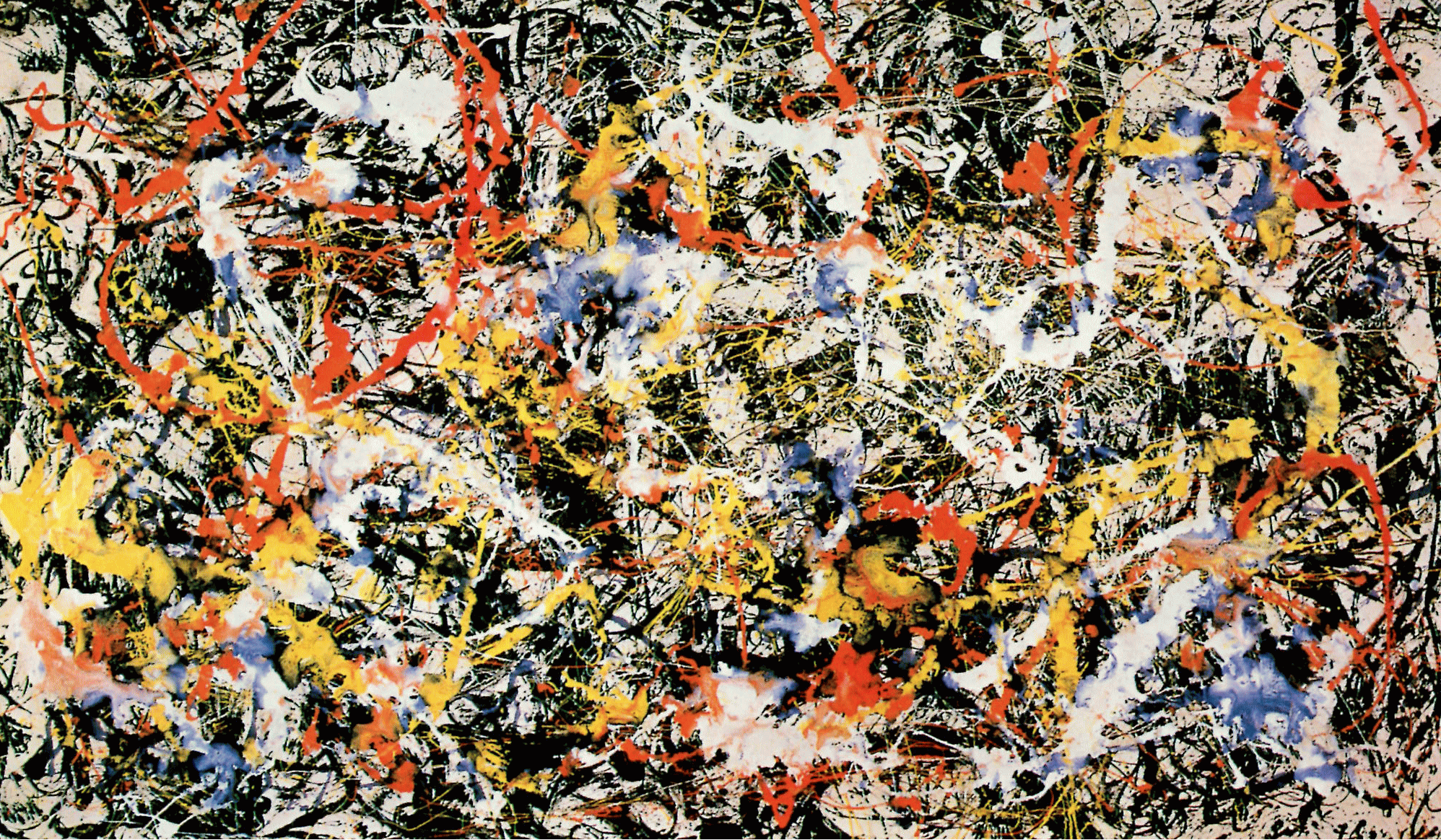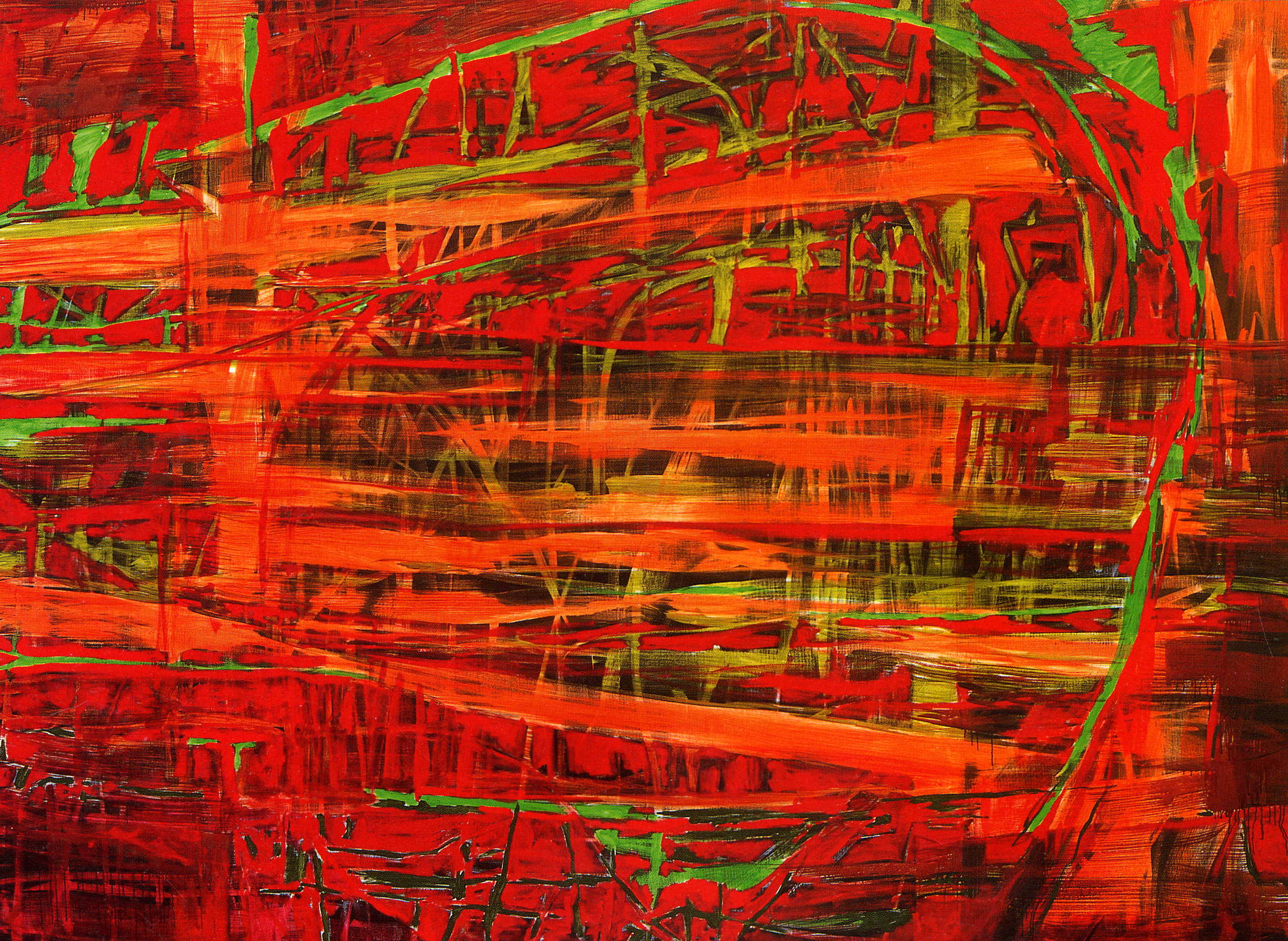��
�Z�U���k�̓��l�̊G���]���āu���F��ɉ߂��Ȃ��v�ƌ�����Ɠ`������B���̂��Ƃ̈Ӗ�������̂͂������[���ܒ~�ɕx��ł��͂��܂����B���̂Ȃ��Ƃ́A��Ƃƌ��͂������ƂƂ��ɕ��ޑ��`��Ƃ̑S�ẮA�����܂Ŋ��ʂ��čl���A���ʂ��Č�邵���A���̏p���Ȃ�����ł���B�u��ɉ߂��Ȃ��A�������Ȃ�ƈ̑�Ȋ�ł��낤���I�v�Z�U���k�̓��l�̐F�ʂ̕s�v�c�ȋ���m���Ă����̂ɈႢ�Ȃ��B��̌��Ƃ���́A�̑�Ȃ���́B�l�����ꂩ��l�@���Ă������Ƃ��邱�Ƃ̈�́u��̍�p�v��ʂ������ʂɂ��Ăł���B�u�F�v�Ɓu�`�v�������ɂ��ׂ��Ȃ̂��A�Ƃ����v�l�Ɋ�Â��Ă���B���̂��Ƃ����̂ɁA�ǂ����Ă����l�͔����Ēʂ�Ȃ����̂������邩�炾�B
�N���[�h�E���l�A�ꔪ�l���N�p�����܂�B����Z�N�v�A���\�Z�ˁB��ƂƂ��Ă͒����Ȃق��ł��낤���B�ӔN�ɂ͂�����������ɐN����Ă����ƕ����B���̕a�������ĕ`���ꂽ�u���@�v��l�͈�㎵�Z�N�t�A�p���̃I�����W�F���[���p�قł݂��B���̎��^�ɂȂ������p�ق̕ǖʂ������ƌ��Ă����ƁA���傤�ǃ��r�E�X�̗̊l�Ɍ��ɂ��ǂ�̂��B�����̐^�Ƀ\�t�@���u����Ă����āA�����ɍ����Ē��߂Ă����䩗m�Ƃ��������������Ă��āA�F�����邮��Ɖ�]�����̐c�����炭��Ƃ����A����Ȍo�����v���o���B��w���o������̓����̖l�ɂƂ��ă��l�͏��F�A��۔h�̈��ƂȂ̂��Ƃ������x�̉��߂����o���Ă��Ȃ���������A�I�����W�F���[�ł̌o���͂ƂĂ��V�N�ł������B
���ꂩ��\���N�Ԃ̔N�����o�Ă悤�₭�A���l�͈�۔h�Ƃ����W�������ɕ������Ă͂��邯��ǁA�Ђ���Ƃ���Ƃ���̓��l�̋��߂Ă������E�̉B�ꖪ�ł͂���܂����Ǝv���悤�ɂȂ��Ă����B��۔h�Ƃ����W�������ɂ�������ă��l�̊G�����Ă���ƁA���t�̖��p�Ɉ����|����A����ȏ�̌������o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�u�E�E�Ȃ��������͂��̗͓����̂Ȃ��ɂ����A���l�̖ڎw�����^�ӂ��B����Ă��āA�������۔h�̓��l�̌��������ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�����Ă���B�v�i���P�j��[���̌��t�����ʂɂ�����A���p�j�̘g�g����蕥��������̊�𗇂ɂ��čĂь������Ƃ��A���������۔h�ƌ����Ă��鐢�E�̃u�F�[������������Ă����̂��B
���l�̔ӔN�ɕ`���ꂽ��i�Q�ɂ́A�`�Ԃ������ĕ`�����Ƃ����p���������Ȃ��B�`�͂ނ���ނ̎v�O�����߂邽�߂̈�̎�i�ɉ߂��Ȃ��Ȃ��Ă���B�`��ے肵�Ă����ł͂Ȃ��̂����A�咣�����ł��Ȃ��B�t�������ꂸ�ɂ��邾�����B���̌`�ԁi�Ⴆ�ΉԂł�����ł���A�_�̈ڂ낤�p�ł�����́j��ʂ��āA�F�Ƃ͂�������ׂ��ł���A�ƌ���Ă���悤�Ɏv����B�����ɂ͂��͂��ۂƂ������̂�ʉ߂����A���������ۂƂ����ӎ��ł��Ȃ��A�܂��Ă₻���ɐ����I�ȗv�f�������������Ƃ�����ł͌����ĂȂ��A�����ɉ�Ƃ�����ŋÎ����Ă���p�݂̂��A�f����Ă���Ǝv���Ă����B���邱�Ƃ̋���A��������݂̂ɐ�S����G��A����Ȃ��̂������ėǂ��̂ł͂Ȃ����A�������N�����̑��s�������Ȃ������B�I�����W�F���[���p�ق̊͐F�ʂ̏W�ς��t�ł鉹�̘A���ƂȂ�A��͂��������։��ւƈړ��𑱂��A�₪�Ē��S��m��ʊԂɏ������Ă��܂��i���Q�j�B���S���͂��ɂ͉����茻�ۂ��N�����Ċl���s�\�Ƃ���Ă����̂��B�������܂������͌��ɖ߂��Ă����B����ꂽ�̃g�[�g���W�[�B
���l�́u���@�v�ɏW�ꂽ��Ƃ�����Ȃӂ��ɐU��Ԃ�ƁA����Ƃ������Ƃ̃_�C�i�~�Y�������炽�߂Ďv���Ԃ����B�����ɂ͌`�Ƃ��Ă̗ʊ����̂Ă��Ă���B���̂Ȃ���i�֊s�j�͈ӎ��ł���A���E�������̂ł���A�ʂ𐄂����铹��ł��邩�炾�i���R�j�B���邱�Ƃ��̂��̂ɐ��肫������ɂ́A�����Ȉӎ��␄���͕s�K�v�ł���B�n���Ȋ��|�̈꓁�́i�����ɐ��ދɂ߂Ċ댯�Ȋ��v�͌�q����Ƃ��āj�A�����̕��ʂł��邱�Ƃ𑣂�����ɂ���ē������Ԃ�ǂƂ���B�G��Ƃ������̎����ʐ�������ɐ����i�߂����ʂɓ�������́A����͂��ɂ͎���s�ׂ�ʂ��Č����Ȃ����̂�\�����悤�Ƃ����������~���Ɛ��炴��Ȃ��B�u�ނ͂��ɂ݂�����̂̂Ȃ��ɁA��Ɍ����Ȃ�������������̂����邱�Ƃ������܂Ō���Ƃ������o�̍s�ׂ��Ƃ����ĒNj����n�߂�v�i���S�j�G��Ƃ͏��F�A���̒��ł̃h���}�Ȃ̂��낤���B���݂�ے肷�邱�Ƃɂ���ē���ꂽ���̂͂��͂⏃���ɐ��_�I�Ȕ��̋��\�ł����L�蓾�Ȃ��B�������^���̔@�����ӂ��������D�����z�ɒ蒅����邳�܂́A���̋��\�̂Ȃ�Ƒs��Ȗz�����ł��낤���B����͎��ɋ��\���������Ă����Ƃ����ɂ߂ċH�ȏꍇ����������B�u���o�������Ɍ�����ԉԂ̐����فv�i���T�j�ł���A�u��I�ł���Ɠ����ɉF���I�ȑs��Ȍ������v�i���U�j�����B���邢�͂��̋��\�����\�Ƃ��ĔF�������l�̋��߂����E�́A�����ē��˂ł͂Ȃ��m���ɗ��j�̕K�R�Ƃ��āA����̃I�[���I�[�o�[�ȉ�ʂɗ��ꍞ��ł��邱�Ƃ�m��̂��B
�Ⴆ�I�[���I�[�o�[�Ƃ������Ƃ���̓I�ȍ�i�Ō����Č���ƁA�����Ƃ悭���l�̋��߂��u���\�v�������Ă���̂ł͂���܂����B
����̗�����t�s���Ă݂�ƁA�|���b�N�̃h���b�s���O����R�������{�H���X�������ԁB���邢�͖l�̓{�H���X�֓��铹��{�������˂Ă���̂�������Ȃ����A���l�̊g�U�������́A�{�H���X�̈łƓ����Ɍ�����B���⓯���Ƃ������͓w�����������Ă���Ƃ����ׂ���������Ȃ����A�����Ƀ|���b�N�u����Ƃǂ����낤�B�|���b�N�̃h���b�s���O�ɂ��Ă̑剪�M�̕��͂��������������p�����Ă��炤�Ƃ��āA
�u�I�[���I�[�o�[�̉�ʂ������Ă䂭�ꍇ�A��i�̒��ł́A�ÓT�I�ȈӖ��ł̍\�����A��ԏ������A�����e���A�o���[�@������F���A������������������邱�Ƃ͓��R�ł���B����Ȃ炻���ɂ͉��ЂƂG��I�v�f�����݂��Ȃ����A�Ƃ�������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�ΏۍČ��I�A���邢�͏ے��I�ȗv�f�͎p�����������A�����ɁA������������F�ʂ̃A���x�X�N�������ɑ��`�I�ȋL���Ɖ����A���ړI�ŋ�̓I�ȊG�抴�o��蒅����͂��@�@������ł���B�v�i���V�j
�����ɕ`���ꂽ�|���b�N�����A���l�ɒu����������ǂ����낤���B�u������������F�ʂ̃A���x�X�N�v�́A�����Ɂu���@�v�̉�ʂɗ�������Ă���B���o�̂��ӂ�����̖L�`�́A�S�g�ɍ~�蒍������̌��ł���B���o�͂܂��G�o�ł�����B
���l�̍�Ƃ͌����̐��E��ʂ��āA���̐^���ߕt�����Ƃ����B���c�G���q�͂��̂��Ƃ��u���o�Ƃ������Ǝ��̂��e�[�}�ɂ�������Ώ��R���郁�^�I�G��v�i���W�j�ƕ]�����B��͂��̍�Ƃ��т��Ă���B���邢�͑ς������Ă���A�Ƃł����������B�N�ɂȂ��Ă����`�Ԃ�ǂ����Ƃ��Ȃ��A�U������F������݂邪�܂܂Ɉʒu�t���悤�Ƃ����B����͂��ɐF���̂��̂ƂȂ��ė��̂܂ܕ��u����Ă���B���łɂ����ɂ́A�����ɓ��铹���p�ӂ���A�F�ʂ̕��˂́u�����ƃC�}�[�W�����ɍ����������v�i���X�j���C�ƈ�̂ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɒ��ꂽ�悪�A�ʂ����ĉԂ�����Ă���̂��A��������Ă���̂��͂܂��ʂ̎��_�Ř_���鎖���ł���B�����ł��̐����������߂��Ƃ��Ă���������Ӌ`�͌�����܂��B�u��Ƃ́A�I�����W�ōl����A�ōl����A���̍l�����Ƃ��낪�m���ɖ�����C��\���Ă��邩�A���Ȃ����A�Ƃ������́A����͕ʎ��ł���A�ʂ̍l���ł���B���w�I�ȁA���邢�͒��ۓI�Ȓ����ɑ�����l���ł���B�v�i��10�j�������������ł͂��邪���яG�Y�͂Ƃ肠�����u���t�̞~���v�𓊂��Ԃ������ɁA�m�炸�m�炸�Ǝ�ȓ��̂ƂȂ��ĕ���Ă������t�̕n�����Ƃ��Ă̖{�����������Ă����B
�@ �`���ꂽ�Ώۂ����ł��邩�A�Ƃ������Ƃ̊m�F�͉�Ƃɂ͂Ȃ��B��Œm�o�����p�́A��Œm�o�ł��Ȃ���p�ւ̕\���Ӑ}�ƂȂ��Ă����B��̗~�]�͈��������Ƃɂ����܂Ŗc���ł��܂��B����͉����Ӗ�����̂��B�Ⴊ���߂�`�Ԃ͏����ꂽ�`�ԂƂȂ�A�m���ɂ����ł́A��͐��E����鑋�ł���B�u������ɂ����Ƃ̎��o�͌��邱�Ƃɂ���Ă����A�܂莋�o���̂��̂��炵���w�ׂȂ��v�i��11�j���A���o�́u�F���̋��Ȃ����ÏW�v�i��12�j�ƂȂ��Ă����A�Ƃ������Ƃ�������B��͒ʉ߂��Ă������̂��t���C�ɂ��������̐��_���`���B�����ɓ���v���Z�X�ɂ����Ď��ȖY�p�͈�̕��@�ƂȂ�A����͎��R�E�̒��ł̖v���ԂƂȂ��Ĕ��M��ттȂ�����A�₪�Ē������ׂ��n�_�����������B�u����v�Ƃ́u����Ď��v�i��13�j���Ƃ��Ƃ������B���̃g�����X��ʉ߂��ď��߂āA�Â��ɂ����Ċɂ₩�ɁA���R�̑S�̐�������̂��B��Ƃ̓L�����o�X�̑O�Ŝp�j����B�������˂����ތ�������A�x�^畏��͏�������B�����ɓW�J�����F�ʂ̋����B
�����ɂ͐Ǝ�ȁu�m�v�Ƃ������̂̉���������Ȃ����̂�����B�����炳�܂Ɍ���ꂽ�F�����B����͂����A�����I���ߖ@�̉��߂Ƃ͐����|�����ꂽ���̂��B�ނ��낻�̑ɂƂ��Ă̓��m�I�Ϗƕ��@�ł͂���܂����B�ߑ�G�悪�w�����Ă����A���R�`�Ԃ���G��I�`�ԂցA���邢�͎��R�̋�Ԃ���G�悻�̂��̂ɓ����Ԃւ̓]���̖��́A�t�s�ł͂Ȃ����낤���B���炭���l�͂����܂ňӎ����Ă͂��Ȃ������ł��낤�B���m�ւ̂�������͍������������ƕ������A���l�̊G��ɂ��̍��Ղ͔F�߂�������̂����A�ʂ����ē��m�I�Ϗƕ��@�Ɋ�Â��č��ꂽ��ł͂���܂��B�ނ��됼���̏d�������`���܂��A�����̈��������ƕ���ł��邤���ɁA���������ė������ꂽ���̂ł��낤�B�������A�v��Z�\�N�ȏ�̎����o����X�͂����ɁA�m���ȋ�Ԉӎ��̍��ق�F�߂�B���̔����ȃY���������ɐ�����Ă��邩�A��������悪��X�Ɏc���ꂽ�ۑ�Ȃ̂��Ǝv���B
�l�̑̓����|�����������l�Ƃ����̑�Ȋ���Ċm�F������A���ꂩ��悢���ɕ��ʂ̒��őS�̐��̉��\�Ȃ̂��A���݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�S�̐��̉́A���邢�͂������ɖ]�ނׂ����Ȃ��s�\�Ȃ��ƂƂ��Ċm�肳��Ă��܂�����������Ȃ��B�����ƕ�����ڍ����邱�Ƃɂ���Ă����S�̂�z���ł��Ȃ����A����������܂Ńh�N�T�Ƃ��Ăł���B�Ƃ����Ȃ�ǂ��ɉ�@�̎肪���肪����̂��낤�B���Ȃ��Ƃ����݈ʒu���m�F���Ă����Ȃ���A���ׂ�������������Ă��܂����A��鍪����r�����Ă��܂��ł��낤�B��̓I�ȉ�����͂����܂Ő���������Ƃ������H�ɂ���Č����ׂ��ł���̂����A��̕��@�͎����Ă������ł���B���̃L�[���[�h�́u���������v�Ƃ������ɂ��肻�����B�Ⴆ�Ύ��̕����l�Ɉ�̃q���g��^���Ă����B
�u�j���[���[�N�̌�Ŏ����K�ꂽ�t�B�����c�F�͂̂������玄���������͂��Ȃ������B ���̌��z�Ƒ��`���p�̒��ɁA���͏\�ܐ��I�̃E�H�[���X������v���������E�E�E�߂���
����A���ꂪ�V������A�ˑR��X�����̔������ň��|����̂ł���B�v�i��14�j
�ߋ���������p���ꂽ��Y�͖l��̐��E�ɏh���Ă���B���̏h���Ƃł������ׂ����𑩔��Ƃ��čl���Ă���ȏ�A��@�̂悷���͌����Ă��Ȃ��B�����ł͂Ȃ����̐�������ΐ������[��Ƃł������Ă邱�ƂœW�J���t�]�ł��Ȃ����B�܂�u���������v�ƌ���ꂽ��X�̎���A���Ȃ��Ƃ����S���t���n�߂Ă����\���N�Ԃ́A�l�̐l�����̂��̂��u���������v�ł���Ƃ������ꂽ���x�̒��ŁA���̂��v�l�����̌��o��p�Ɉ��������Ă����A���̂��Ƃւ̔��Ȃ����ւ̏o�����������Ă���悤�Ɏv���Ă���B
������̔��_�����邾�낤�B�u���������v�ł��邪�̂Ɍ��镔���A�ہu���������v�ł��邩�炱���A�V�������̂̑n�������R�ɕ\���ł���̂��A�Ƃ�������B�������n���Ƃ������Ƃ��b���l���Ă݂Ă����炩�Ȃ悤�ɁA�����ȓƎ����A�S���V�����n���Ȃǂ��蓾�Ȃ��B��i�ɔ����������߂��̂��Ƃ�ϋɓI�Ɏ�����悤�Ƃ���|�X�g�E���_�j�Y����i�삷���ł͂Ȃ�����ǁA�A�ȂƑ������j�̒��œ`���͕K���V�������̂̐����ɐH������ł��邵�A�߂�ւ��Ăł��������т���̂��B�����Ď��R�E�̒��Ƀ����C�N�ł��Ȃ��`�Ԃ�{���͕̂s�\�Ȃ��Ƃł���ȏ�A�͕�͏�ɑn���̌��_�ł�����̂�����u���̖������͖̂����v�ƌ������Ƃ��ł���B�]���āu���������v�Ƃ������t�̓A���`�m�~�[�ȗ��`������Ɋ܂�ł����Ԃ������B���̗��`���������Ƃ������Ƃ��A�ނ��뎲����]�����錴���͂ɂȂ�A�v�l����뉟������p���[�Ƃ��Ȃ肤��̂��낤�B���̂��Ƃ�ʂ̂������ł���Ȃ�u�I�C�f�b�v�X�E���A���Ȃ킿���e���E���Ă������̂ɂ��Ă��A���̕��e�̑��݂�O��ɂ��Ĕ��W���Ă������̂ł���B���Ȃ킿�������d��������́v�i��15�j�ƌ������Ƃɂ��Ȃ�A���������Ӗ��ł̓f�B�A���N�e�B�N�ȕ��@�_����݂����Ă�����B�����Łu���v�Ƃ͉��ŁA�ǂ�����ׂ����Ƃ������Ƃ��A�ʂ̎��_�ōl���Ă݂����B
����ɂ���ē��{�̎v�z���傫���h�ꓮ���A����ȑO�ƈȌ�Ƃł͊u��̍������������Ƃ��A�܂��L���ɗ��߂Ă��������B���̍ő�̕ω��͓��{�����@�ɖ��L����Ă�����̂��B�Ƃ�킯����̋@��ϓ��͐�㖯���`�̏ے��Ƃ��Ă������ł���B���̏������ʂ����������͑傫�Ȑ��ʂƂ��ĔF�߂�ׂ��ł��낤�B�N������������������錠������ɂ���A���̕ۏ����@�̐��_�Ȃ̂��A�Ƃ����܂ł͏����Ȃ̂����A���̐�ɒ��ӂ������B�����Ƃ����ӎ����邢�͖���I�ȉ^�c�Ƃ������̂��A�ꗥ�ɂ������S�Ă̕���ɂ����ē��Ă͂߂Ă������Ƃ����A���̐��}�Ȑ�㏈���ɏ悶������\���̘_���ɖ����������Ă���͖̂����ł���B�����ĉB���ȉR���Гh���Ă����̂��B���̂Ȃ�A���݂������|�p�\������ɑ����̏����Ɂu�ʁv�̎��_�͋����ꂸ�A�W�c����́u��E�v�͂�������e���ׂ�����̑̐����������Ȃ����R�Ƃ��čs���Ă���ɂ����āA�����|�p����ł���̂��B���{�̋ߑ㉻�̒��ŗ����x��A�����ĕn��ɂȂ��Ă����������ł�����B���オ��̋���ς���͌X�l�̗���̑�����������邱�Ƃ͎���ł���B
���オ�苳��ɂ��Ă̌����𐳂��Ƃ��A���x�Ƃ��Ă̓��{�̕����s���̂�������^�⎋����Ă���B�����|�p�����ւ̉��炩�̉����𐭎��I�ȑŎZ�����Ɏ��{�ł������͂ǂ̂��炢�������̂��낤���B�i�S���������Đ������𗍂߂��Ƃ��Ă��j�����Ȃ���ʓ��{�̗��j��R�����Ă�����Ȃ��̂͗L��͂��Ȃ��B�����ɂ͌|�p�ɑ��鍑���S�̂̈ӎ��̖�������̂����A���ꂪ�H�����Â��邢�͎Љ���S�ʂƓ����ʂ̃��x���Ō|�p�����邱�Ƃ��K�v�ł���A�Ƃ��������̊F���ɓ�������Ԃ������Α����قǁA�����I�ɂ͗����x�ꂽ�n�R���Ƃ��Ă̂������Ƃ�Ȃ��B�u���̂܂܂ł͓�����̈����Ԃ݂����ɁA�����͂�̋��ꂪ����A����͓��{�̐��_��n���Ȃ��̂ɂ��A���{�S�̂̐����ɂȂ���B�E�E�E�|�p�͂��ꎩ�̂ŁA���Ƃ̍����ɂȂ���d�厞�v�i��16�j�Ƃ̌��t��f�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���͋}��v���Ă���̂����A���̏ő����͍��ƑS�̂������Ƃɖ����Ȃ��܂�A���Ƃ��Y������A���܂����̑�����N�������J���Ă����i�ς��ꂽ��Ɍ͗L�蓾�܂��j�B
�m���Ɍ��݂̌|�p���������Ă����Ƃ��A�l�I���x���ł̔����͓���������ɂ��̎����ł͂Ȃ��Ƌ���Ă���悤�Ɍ�����B��������q���邲�Ƃ��A�|�p�n���Ƃ������Ƃ́A���̌̑����ɂ��Č��l�ɗ�����A���̈������ɂ߉��߂��Ă������Ƃ���x�N�g����K�R�I�ɗv������B��{�I�ɂ͌ɗ����A�邱�Ƃ���n�܂肻���Ă��̗���ōk�����Ƃ̈��ł����Ȃ��B�c�O�Ȃ��炱�̂��Ƃ��㖯���`����͌��������Ă����B�������m�炸���]���ꂽ������`�͌|�p�Փ��̐X���܂ŐN�Ƃ��A�Ƃ��Ă̎�����Ǝ㉻�����Ă����B�������ꂽ�Ƃ���Ɍ��������]�����܂�悤���Ȃ��B���̂��Ƃ�Ԑ��쌴���́A
�u���������܂̐��̒��́A���̂��Ƃ𗚂��Ⴆ�邱�ƂɂȂ����B��������ē����I �ɋ������u�Ԃ̖��A���̑O�q�̖��剻�ł���B�O�q���݂�ȂŁA���x���A�Ƃ����o��
������Ԃ��A��㖯���`�ɂ�鉷�����ʂƂȂ��Ă�����Ă���B���R�ƕ����Ƃ��� ����ΐ�㖯���`�̋��璺�ꂪ�A�ӂ����ю������̓��]�������Ă���B�ڂ̑O�̖�肪���ꂽ���ɁA���R�ƕ����Ƃ������̐��̖ԗ̂��o�Ă���ƁA���Ƃ͂Ђꕚ���ȊO�ɂȂ��Ȃ��Ă���v�i��17�j�ƌ��B
��㖯���`�̐��ʂƂ���ɂ���ĕ��ꂽ��������x�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������ł͂��̂��Ƃ�_����C�ɂȂ��̂ŁA��㖯���`�̘c�݂��w�E����ɗ��߂Ă��������B
�ӎ��͌p�������B���̂��Ƃ܂��Č��A�S�Ă��s�킩��n�܂������̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩��B�Ƃ肽�ĂĐ�c�A����咣����킯�ł͂Ȃ�����ǁA�����̈����p���͕K�v�s���Ȃ̂��B�łȂ���c�m�`����������l�ނ̗���͎����I�ɓr�₦�Ă��܂��ł��낤�B�l��̐l���ƕ����̓A�v���I���Ȃ��̂Ƃ��āA�ڂɌ����ʎ��ŃA�o���Q�[���ƂȂ����Ă���̂��B�S�Ă��������Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A�������̑I���̌�ɖl��̌��݂͑��݂���B������A��u���Ƃɕϗe���Ȃ����̂͂Ȃ����A���̕ω��̒���s�f�ɘA�����Ă����c�̂悤�Ȃ��́A�g���Č����ΓƊy�̒��S�ɂ����镔��������A���̎����������A�ȂƑ��������̊j�ƂȂ镔���ł���ƌ�����B���̂��Ƃ́A���l���m���ɁA���̋�Ԉӎ���ϊ����Č���̃I�[���I�[�o�[�ȉ�ʂɗ��ꍞ��ł���Ƃ����A��ɘ_�������l�_�̔@���A�����Ȃ��̂Ƃ��Ă���B����͂����v�l�̓]���ł��邵�A�g�݊�����ꂽ�p���_�C���́A����I�ȋT����Ă��邩������Ȃ��B�p�����ꂽ���̂��ǂ��ɂ������ł��Ȃ����_���[�W���Ă���Ƃ����Ȃ�A���ɕ����ł̉𖾂����݂��Ƃ��Ă��Ӗ��̂Ȃ����ƂȂ̂��낤���B���̂悤�ɂ��v����B���������ۂɌ@��N�����Ȃ���Ό����Ă��Ȃ�����������B�����Ɏc���ꂽ�͂��ȉ���肪����Ƃ��āA��������������͕��@��������Ȃ��B
�Ƃ���ŋ�Ԉӎ��̕ϊ��Ƃ������Ƃ����������˂�����ōl���Ă݂�ƁA�ǂ��������ƂɂȂ�̂��낤�B��Ԉӎ��̍��فA�܂��̓Y���Ɗ������Ă��悢�B���l�̎���ɐ����������ʐ��̊l���A���邱�Ƃ̋���Ƃ���݂̂ɐ�S�ł���G��̑��݁B�F�ʂƕ����̍K���ȍ����A�F�ʂւ̑f�p�Ȗ₢�|���Ƌ^�O�̂Ȃ������B�����ȕ����Ƃ��Ă̋���A����炪�r���������������Ƃ���Ƃ��āA�ʂ����Ċ��S�ɑr�����Ă��܂����̂��낤���B
�G�悪�G�悾���Ŏ����肽����A����͌���������A�F�ƌ`�Ԃ������ɊҌ��������ۏՓ��̐�������ł��������Ǝv����B���̋ߑ�̂Ƃ����ɗ��A�G�~�[���E�x���i�[���A���[���X�E�h�j�A�V���v���}�e�B�X���ƍ\����`�A���邢�̓J���f�B���X�L�[����h���A���Ɏ���R���Z�v�g�́A�����n���������ۊG��̉�����z������A����ɊG�悪�G��ł���݂̂ł͏����Ƃ��ĕs���ł���ƈًc�\�����Ă��n�߂��̂��B�܂�A�G��s�ׂ��̂��̂ɕt������L�`�̈Ӗ��ł̃C�����[�W������E�o���Ă��邾���ł͂��͂⎞��͎t���Ȃ��Ȃ��Ă���B�������������Ƃ��Ă̈�̔g���A�W�����A���E�V���i�[�x����A�f�B�r�b�g�E�T�[���Ɍ�����ٕ�����i���e�B�u�̓����ł���A�����ɂ͖\�́E���E�G���X�E�����E�G�C�Y�Ƃ���������̒����Ƃ��Ă̍��������f����Ă���B���̓�����F�߂Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�ł͈�̂���ȑO�̏������ۊG��͊��ɓ������ꂽ�n�����N���݂̂Ȃ̂��ƒf������ɂ́A���ꂱ���T�[����V���i�[�x���ł͗]��ɂ������ȗ]�k�ł����Ȃ��B���I���Ƃ��Ắu���ׁv�͒P�Ȃ�u�����v�ł͌����ĂȂ��͂����B
�G�悪���ɕ�������ł��鏔�v�f�A�Ⴆ����͌`��F�ʂȂ̂����A�����������݂̂̂Ō��ɂ́A�G��͕s�тɉ߂���Ƃ����A�O�݂��鉽���A�O�q�����V���i�[�x���́u�M�v�Ƃ����I�u�W�F���������ނ��Ƃɂ��C�����[�W�����̑Ŕj��A�L�[�t�@�[�̕�������荞��ł������@���G��̒��j�ɓ˂����n�߂��Ƃ��Ă��A����͏��F���j�̒��̏����ȗh��߂��A�����Ă����Γ��ɂ�鏬���Ȕg��ɂ����Ȃ��B�g��͂������`�d���Č`�𐬂���������Ȃ����A����������������Ă�����B�����V���i�[�x����L�[�t�@�[���Q�̐V�\����`�ҒB�ɂ���Ďw�E���ꂽ�A���̊��o�I�ȕ\�o�́A�h�C�c�\����`�̌������𔗂�������B�u���̕������́A�\�㐢�I�I���E�̕������Ƃ͑S�����ƂȂ�A�������ꎩ�̂�s�����ȏے��̂悤�ɑ��݂����āA���ݓI���N�͂������Ă���̂ł���v�i��18�j���؍_��Ɍ��킵�߂��u���ݓI���N�́v�͓��ɃL�[�t�@�[�ɂ���ĔF�߂��邱�Ƃ��m���ł���B�����������ł͈���������ė��j��k�サ�������z���ėŐ��ォ�猩���낷�ƁA�댯�Ȋ��v�������ɉ�������Ă���̂������B�ꂵ�Ă���悤���B
�`���s�ׂ̂��Ƃ�A���ʏ�ł̊G�̋�Ƃ��������̎��o���B�F�ʂƕ������K���ȊW�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A����������A�̍s�ׂ̒��ɁA�܂��₢�l�߂�ׂ��������̗v�f�����݂��Ă���̂ł͂Ȃ����H
���̂��Ƃ��G�搧��̎��H��ʂ��Ĕ��\���Ă����A��̎���ɋ��߂Ă݂悤�B�܂��A����d�͂̈�т������ې���ɋ��߂���B��̓����Ƃ��Ă̓��ƊO�Ƃ̘A�W�B���Ȃ̌��Ƃ��̎��Ԃ�a���A�\���I�ɓ��������Ă����p���́A���Y�~�J���Ȑ������A����������ɖʂƂ̑Λ��Ƃ����G��̐��������������n�߂�B���������Ȃ̃��W���[����ʉ߂��ĕ`���ꂽ�X�g���[�N�����݂��A�����ɐ��E�̐��A���邢�͊G��̎����́A�݂��݂�������ɉf���Ă���B�܂����{�z�q�̌��������ꂽ��z�ƊG�̋�̍��݉��͂ǂ��ł��낤���B�����Ē����ĔV�̈�A�̊G�搧��ɂ����Đ����ꂽ��Ԃ̐V���ȓW���B�����̕\���́A����̊G�悪����ȏɂ�����Ă���ɂ�������炸�A���R�Ƃ��ĊG��ł��邱�Ƃ̏j�����ꂽ�W��ł����ĂĂ���Ǝv����̂��B
�F�ʂƕ����i�F�ʂƂ́A�I������ӎu�ɂ����āA���邢�͐��_�ƌ����ւ��Ă��悢�j���K���Ȉ�v���݂Ȃ��Ƃ��Ă��A�����ɒl���Ȃ��B�s�K�ȊW��Q���̂Ȃ�A�ނ��댻��Ƃ������オ�s�K���̂��̂Ȃ̂��낤�B���̕s�K�̒����猩�������ׂ���Ƃł���ƐS���ׂ��Ȃ̂��B
��Ԉӎ��̍��قƂ́A���邢�͂����������邩������Ȃ��B�������Ƃ��ĔF�߂Ă����Ƃ����ߑ�̈Ӑ}���ꂽ��Ƃ̒��ɁA����͕ʂȂ�����������Ε����I���藧������C�����[�W�����ֈڍs���Ă����v���Z�X�����̍�Ƃ̒��Œf�����Ă������Ƃ��Ӗ�����̂����A��������������o�ċߑ�͎��̂��Ƃ���Ă����B�܂蕨�����犴��ړ�����菜���Ƃ������Ƃɂ���āA���o�̏���������w���߂�������ʂ����Ă����̂��B�F�̎��������A�����o����x�E���Y�����Ă��炳��̏�Ԃɒu����������ɁA���߂đg�ݒ������Ƃ��\�ł͂Ȃ����A����͐V�����_�C�i�~�Y���̉ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�S�̐��̕����ɂȂ��邩�ǂ����͕s�������A���Ȃ��Ƃ��s�ׂ̈�̐���ɂ͐��蓾��Ǝv����A�ƁB
�����������ɂ̓~�j�}���Y�����ʂ������Ƃ��ĉʂ�����Ȃ������u�C�����[�W�����̖��E�v�Ƃ������Ƃ������ɕ\����̂ƂȂ��Ę_���̗����ɂւ�t���Ă���̂���m���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l�炪���łɌo�����Ă����~�j�}���A�[�g����R���Z�v�`���A���A�[�g�ɂ����闬��̒��Ŏ�����Ă�����i��ʂ��čl���Ă݂�Ɓi���Ȃ��Ƃ��e�[�[�ɑ���A���`�Ƃ����W�̉�����ɂ����čl����Ȃ�j�A�u�|�p�v�Ƃ����g�g�����O���Ă͍�i���������Ȃ����ƂƓ������A��i�̒�����C�����[�W�����Ƃ������́A���Ƃ��u���̂Ȃ��̔��v�ł����Ă��A���C�Ȃ�u��ΓI���v�ł����Ă������A�l��̎��o�͈��������ɂ������ɉ��炩�̍��Ղ����������Ă��܂��B���̋L���ɗ��ݕt�������o�̍�p���G��̍����ɐ�����Ƃ��A�~�j�}���X�g�B�����ʂ��̂Ăė��̂Ɍ������������������ł���B�����ɕ��ʂɂ����Ă͌K�R�����̍�i�ɂ�����������悤�ɁA����߂Č��肳�ꂽ�F�ʂ̎g�p�A�ۂނ���F�ʂƂ����A�\��𑽂��܂݉߂�����̂�ے肵�A�����܂Ńx�[�V�b�N�Ȗ��ʐF�ɂނ��킴��Ȃ��ɒǂ����܂�Ă������v���Z�X�Ƃ��Ă̗��j���X�b�L���ƌ����Ă���B
�����ɂ��ăC���[�W�����Ƃ������̂̒�`�A���߂�������Ƃ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A�Ⴆ��\�l�N�ꌎ�ɃM�������[��c�i��19�j�ɂ����ďЉ�ꂽ�u���s�v�Ƃ��������l��Ƃ̍�i�ɂ��ċL���ꂽ��t���v�̃e�L�X�g��`�����ƂŁA���ꂪ�����o�����Ǝv���Ă���B
�u���s���͂Ȃ��E�E�E����������Ă��Ȃ��v�ƌ���t�̐^�ӂ��ǂ��ɂ���̂������Ă��Ȃ��B���s�����Ȃ�����������Ȃ��A�Ȃ���̎��͈̂�̂ǂ������V�����m�Ȃ̂��B���̂悤�ȉ����������̐��ɑ��݂���͂��͂Ȃ��B�����͕����Ɍ����������Ȃ��A�u�������v�Ƃ������݂��Ԃ̏o��������O�ɍ�i�͗�R�Ƃ��āu�����v�����I���Ă���B�������u���ʁv�ɒu���ꂽ�F�ʂ͂��łɁu���鉽���v���A���ꂪ�ǂ������Ӗ������������Ȃ��������ł��ʊԂɁA���B�ɉ�X�̊���˔����`�d���Ă��܂��B������悵�u�L���v�ƌ��Ă��A�C�����[�W�����̖o�łǂ��납�C�����[�W�����̖S��ɂ�������ƕ������������Ă���ł͂Ȃ����B�u���ʁv�ł��肩�u�����v�ł���ȏ�u�E�E����Ȃ܂܂ɐ������Ă���v���Ƃ͕s�\�ł���B���̂��Ƃ������ɃC�����[�W�����̂���l������Ă���B
�u��Ԉӎ��̍��فv�ƌ����A���邢�́u�C�����[�W�����̖��E�v�ƌ�������ǁA�����ɂ����锽���������x�N�g���ꎋ���ɕ������݂A�~�j�}���Y�����z���Ă����\���Ƃ͈�̂ǂ�ȃX�^���X�����̂��낤�B���邢�͂��ꂪ�\�Ȃ̂��B�܂��͂��������ߑ�̖ژ_���͉ʂ����Ď��ۂɍs���l�܂��Ă��܂����̂��낤���B���̂��Ƃ����̐߂ł��������ڂ����q�ׂĂ݂����Ǝv���B
���P �ҖM�v��i�W�U�u�N���[�h�E���l�̐��E�v�͏o�V��
���Q �n�����q�͈�۔h���u���S�̑r���v�ł���ƋK�肵�u���S��r�����邱�Ƃ���������������Ƃ��A�r�����ꎩ�̂͂������ʂ̂��Ƃł���v�i�u�፷���̕ϊv�|��۔h��ǂݒ����v������w���{�w���V���|�W�E���A��\�O�N�\�j�ƌ�������A��ƂɂƂ���
�i���邢�͎l�p����ʂ�O�ɂ��āj���S�������Ƃ������Ƃ͋ɂ߂ċ��|�ł���p�j�b�N�������N�������Ƃ��B����͍���ɂ��Ďn�߂Č����邱�ƂȂ̂����m��Ȃ��B���̂Ȃ�ǂ̂悤�ȍ�Ƃł��i�Ⴆ�V�F�C�v�h�E�L�����o�X�ł��낤�Ƃ��j�A�፷���̑O���ɓV�ƒn������A���邢�͐����ɂ����ꂽ��ʂɗ������Ƃ��Ă̎����̑��݂����邩�炾�B�܂�፷���͕K�����̗��r�_����u��v�𒆐S�Ƃ��A��������~�����镨����������B���̎����璆�S�������S�̐킢���J�n����A���̐킢������Ēʂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ����炾�B�ނ���u���S�̑r���v�͉�ƂɂƂ��ėL�蓾�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
���R �u���͕��̗̂֊s�Ƃ��āA���邢�͋��E��ݒ肷����̂Ƃ��āA���邢�͏����݂��u�Ă���̂Ƃ��đ��݂���B����ے肷�邱�Ƃ́A����䂦���̂╨���̃��x�����ĕ��ՓI�Ȃ��̂ɐZ�����邱�Ƃ��Ӗ�����v�i�u�A�[�g�E�H�b�`���O�v�J�숭�A���p�o�ŎЁj�B�ʂ��̂Ă�Ƃ������ƁA���邢�́u���̔ے�v���u���ՓI�Ȃ��̂ɐZ������v���ǂ����A���̂��Ƃ��G��̎��H�ɂ����Ďc�O�Ȃ��玩���͂܂����f��~�i�G�|�P�[�j�̂܂܂ł���B���������̂��Ƃ͌����Ă��悢�ł��낤�B�܂�u���S�̑r���v�ɂ���āA�G����\�����Ă�����ׂ��Q���ے肳��Ă����A�����������ۂ������N�����Ă��邱�ƁB����͍\���̔ے�Ɍ������A�F�ʂ͎����ƖʓI�ȗv�f�ŏ�������Ă���B
���S �F�����p���u���E���p�S�W10�v�͏o�V��
���T �O�f��
���U �O�f��
���V �剪�M�u���ۊG��ւ̏��ҁv��g�V��
���W ���c�G���q�u�G��̎v�l�v��g���X
���X �{��~�u���p�j�Ƃ��̌����v�������_��
��10 ���яG�Y�u�ߑ�G��v�V������
��11 �������E�|���e�B�u��Ɛ��_�v�݂������[
��12 �O�f��
��13 ����
��14 ���r�B���X�g���[�X�u�߂����M�сv�i���j�������_��
��15 �������v�u�₳�������p�v�ǔ��V����
��16 �g�c�G�a�u�����V����l�N�ꌎ�\����[���v���
��17 �Ԑ��쌴���u�痘�x�E�����̑O�q�v��g�V��
��18 ���؍_��u�ǔ��V����O�N�O���ܓ��[���v���
��19 ��t���v�u���ʂɂƂǂ܂�G��E���s�v�W�e�L�X�g
 |
| ���l�u���@�v |
��
���̋ߑ�̖ژ_���͍s���l�܂��Ă��܂����̂��H���̂��Ƃɂ��āA���ۂ̍�i�Ɨ��j�I�W�]�ɉ����ĐU��Ԃ��Ă݂�̂͑�Ȃ��Ƃł���Ǝv����B
�܂������ł͏o���_�����l�ɂ����A����ȍ~���猻��܂ł̊ԂɁA�������ꂠ�邢�͏����Ă������l�X�Ȕ��p�v���Ƃ��̍�i���A�Ƃ�킯���̘_�|�ŏd�v�Ǝv���邢�����̗���𒆐S�ɁA�_��i�߂Ă��������Ǝv���B���̂������̍ŏ��͂܂��A�����I�����Ɍ��ꂽ���ۊG��Ƃ���ɑ����~�j�}���Y���ł���B�����ă~�j�}���Y����G�������t�H�[�}���Y����A�o�E�n�E�X�^���Ƌߑ�f�U�C���̔��z�B���邢�͓��������I�ɐ��E�̊e�s�s�ŋN�����R���Z�v�`���A���E�A�[�g�Ƃ��ꂩ��ٓ��������{�́u���̔h�v�Ƃ��������ł��낤���B�����̗�����T�����Ă������ƂŁA�s���l�܂����Nj�Ԃɏ����ł��������J���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂��낤���B
���ۊG��̔����Ɛ��藧����ǂ��Ă����ƁA��̑傫�ȗ��ꂪ���邱�ƂɋC�t���B������������咪���Ƃ��ĕ�������̂͑�������������悤���B�ނ�����݂ɍ������킳��A�O��ɉ���������������̂ƍl�������B
�܂��J���f�B���X�L�[�̎v�l�V�X�e���A�����h���A���ƃf�E�X�e�B���A���V�A�A�o���M�����h�ƍ\����`�A�V���v���}�e�B�X���ɂ�����}���[�r�B�b�`�A�����͂�����������̏����`�Ԃ���̓I�`�ە��Ȃ��ɁA�ǂ��炩�Ƃ����Ɗw�I�`�Ԃ���Ƃ��ĒT�����Ă������^���ł���A���̌�ɑ����~�j�}���Y����y�o�����B
�����̗���Ƃَ͈��Ȃ��̂Ƃ��āA�L���[�r�Y���A�t�H�[�r�Y���A�V���[�����A���X���A�����Ē��ە\����`�Ɍ��т����ꂪ����Ǝv���B���l�̊G��͂ǂ��炩�ƌ������̗���ɋ߂��B���Ƃ��Ƌ�ۓI�`�Ԃ���o�����āA�����P�����Ȃ����f�t�H�������Ă����Ȃ���A�`�ƐF���������Ă��������̂��B�|���b�N��u�H���X���V���[���I�ȉe�����܂݂V���ȍL����J���Ă����B�������Ă݂�ƃt���C�g�ɏے����ꂽ���r�h�[�I��O��A�����O�̌l�ɂ�����썰�̏��ݘ_�Ƃ����A�����ߑ��w����̔��z��ʂ��Č���镔�����m���ɑ��݂���B
����͂Ƃ������A���_�I�Ȃ��Ƃ��猾���Ă��܂��A���̓�̎v���̊Ԃɂ͑傫�ȗ���������A�t�H�[�r�Y������n�܂����ߑ���p�̗���A�}�e�B�X�̐F�ʂ��o�ăV���[�����A���X���Ɏ���A�����ăA���t�H��������A�N�V�����y�C���e�B���O���z���āA��قǘ_��������d�͂⏼�{�z�q�̊G��̒��ɗ���Ă��郂�_�j�Y���ɉc�X�Ƃ��Ĕ|��ꂽ�\������̌�����ł��낤�B����͍����I�̔��p�v���Ƃ��Ă��嗬�̈�𐬂����̂��B
����̑傫�Ȓ����A�w�I�`�Ԃ�ǂ����߂���Ύ�`�̉ʂĂɁA�l��͉�������悢�̂��H�Ⴆ�ΑO�L����������u�M�����ہv�ƌĂԂƂ���Ίw�I���ۂ́u�₽�����ہv�Ƃ��Ăׂ�B���̗�߂��N�[���Ȏ����������̂��l���Ă݂悤�B
�@�����Ŋj����̑z�������Ă݂�ƁA���p�̎��ʂȖʂł̐��i�����R�Ƃ��Ă���B���ۊG��̍���̖ʁA����̓~�j�}���Y���ɏW���Ǝv���B�j�̓��������̕�������Ƃ��Ă��邲�Ƃ��A���p�̏��v�f���ŏ����̒P�ʂŌ`�����邱�Ƃ��A�����ł̃e�[�}�ł�����B�c�m�`�̕��q�\�����𖾂��ꂽ�̂����O�N�ł���Ƃ������Ƃ��炵�Ă��A���j�̓�����������������̂����A�����������~�j�}���A�[�g�Ƃ́A�����Z�̃A�[�g�ł��������̂��B�ǂ��܂ň����悢�̂��A�������Z���͕�������`���Ȃ�����ɂ͉��Z���ɓ]���Ă����B�]�����悪�A����̉ߏ�Ȃ�\���ɒʒꂵ�Ă��鐫�i��тсA���̂��Ƃ�̌�������ƂƂ��ăt�����N�E�X�e���i�ނ̋O�Ղ��������s�������A�����͂��̗ǔۂ�ʂƂ��āj������̂����A���܂�摖�肷��͔̂����悤�B
�@�~�j�}���A�[�g����i�ʂ��猟�����Ă݂�Ƃ��̐��i����������Ƃ��Ă���B�Ƃ��ɂ��̗���̓����Ƃ��ẮA���ʂ������̑��`�̂ق��ɋ�������Ă���悤���B�Ƃ������Ƃ́A��قǂ������A�N�V�����y�C���e�B���O���邢�͐F�ʔh�ƌĂꂽ�}�[�N�E���X�R�A�܂��̓T���E�t�����V�X�̃t�B�W�J���ȕ\������ɔ��I�ȃC�����[�W�����ʑ��`�̒��Ɏ��������ƂƑΏ̓I���݂Ƃ��Ă���B
�@�ȑO�A�h�m�`�w�M�������[�ɂĒ��ʐS�Ƃ����؍��l�̍�i�i���P�j����ɂ������Ƃ�����B���̎��Ⴊ�߂炦�����̑��`�ɖl�̎v�l����v���Ȃ�����u�͂��䂳�v�������Ă����B���̂͂��䂳�͈�̂ǂ��������̂��B��������Ƃ̔����i��i�j�Ɖ�X�̊Ⴊ����̏�ŋ��L�ł��Ȃ����Ƃ͓���悭���邱�Ƃ����A����ɂ��ĒQ���Ă݂Ă��n�܂�Ȃ��̂����A���́u�͂��䂳�v�̑�����ǂ̂悤�ɕ߂炦�Ă������A�߂炦���̈Ⴂ�ɂ���Ă͗l�X�ȉ��߂������邾�낤�B���̂��Ƃ��m���߂邱�Ƃ��u���فv������ׂ��Ƃ���Ɉʒu�t���邱�Ƃł����낤
�@���Z�Z�N�Ƀj���[���[�N�ŊJ�Â��ꂽ�A�v���C�}���[�E�X�g���N�`���[�Y�i��{�\���j�W�ɂ����Ē��ꂽ�T�O���A�~�j�}���Y���i�ŏ��̒P�ʂŎv�l����j�ɓ]������Ă����̂����A���̋ɏ��ŁA����I�Ȃ��̂���ؐ@����������i�ɂ́A�ǂ��ɂ��₽�����̂����c��Ȃ��B���₻�ꂷ����ے肳��Ă����悤���B�P�Ƀ��j�b�g�Ƃ��Ă�����ɃS���b�Ɠ����o����Ă�����́B�����ɂ͌l�I�ȗ���ł��̂����郌�x�������S�ɐ�̂ĂĂ���B�m���ɕ����̎��\���₻�̐����Ƃ��Ă̖{���I���藧���͖����ɓ`��邪�A�����܂łł���B�Ȃ��i�A�ہA�|�p�Ƃ����T�O�⌾�t�Ō��K�v������܂��B�l�Ԃ̎�C�⊾���������n�܂���̂��A���������u�v�Ƃ��Ă̕\���𐬗������Ă������Ƃł͂Ȃ��̂��B��̍��Ղ��������邱�Ƃʼn������܂��̂��H���܂�邱�Ƃ������Ƃ��Ȃ��̂Ȃ�A�|�p�Ƃ����T�O�̓y�U���狎��ׂ��ł��낤�B���̂��Ƃ���̔��ȂƂ��čl���Ă݂�ƁA���Ȃ̃��W���[�����炵�����_�͗L�蓾�Ȃ����A�����ɕԂ��Ă��铭�������ł����Ȃ��B�{��~�́u�|�p�����݂��Ȃ����Ƃւ̕s�\���v�ƌ��������ǁi���Q�j�A����ɏK���Č����Ă݂�u�C�����[�W�����@���邱�Ƃւ̕s�\���v�Ɗ����Č�邱�Ƃ����Ȃ������Ӗ��Ȃ��Ƃł͂Ȃ��������B����́u��Ɓv�Ƃ������t���z���Ă������ƂɂȂ���A�u�����v�Ƃ������t��p�ӂ���B�l�̃R���e�L�X�g���猩�������Ƃ��G�搧��̍����ɐ����Ă݂�ƁA��������h�����Ă�����̂�����A���̔h�����u���فv�ƒu��������A��X�̎����Ɉ�����x�N�g�������_�C�i�~�Y���������n�߂�̂����B
�Ƃ���ł��̎���̔w�i�i���Z�\�N��j�߂Č���ƁA�l�I�ȉ����͐����I�Ȉ��͂̂��Ƃɖ����ɋ�������A�s���Љ�̒��Ŗ��v���Ă������B����Ƃ͔��ɁA���ʂɊ��Z���ꂽ�O���t�ⓝ�v�ɂ���ĕ\���ꂽ�����I�Ȍ����ւ̌X�ɁA�v�������삳��Ă����̂ł���B�Z��N�ɐ��������K�J�[�����̐l���q���́u�n���͐������v�ɏے�����邲�Ƃ��A�K���ȉȊw�̐M���薾�邢������\�����Ă���B�Z�ܔN�Ɏn�܂����k���́A�K�����ꂽ�j���[�X����M����݂̂ō���̎����Ɍ����Ă������A�����ĘZ��N�ɏ��߂ăA�|���\�ꍆ�Ől�ނ����ʂɗ������Ƃ��A�F���ւ̖����ő���ɖc��A�����Ȃ��Ƃ��|���e�B�J���ȃv���p�K���_�͂��̂悤�ɓǂݎ�邱�Ƃ��������Ă�������ł��������B�i�����������Ƀx�g�i���̍������������A���\�N��̋ꂵ�݂��n�܂�Ƃ��ł��������̂����B�����Ă����ɉ�������Ă���B���ꂽ���̂́A�ǂ����ő��l���Ɍ��������ׂ�p�ӂ��Ă����̂��m���ł���j�B
�@�u��v���́u�m���v���A���̑g�ݗ��Ă�_�̍��i�ɐ����ĕ\���������̂����p����͂��߂�B����͌|�p�̏�ɂ������邱�Ƃł���A�����R���Z�v�`���A���E�A�[�g�ƌĂ����̂̏o���𑣂����B����͂��̓~�j�}���E�A�[�g�̌Z�핪�ɂ����鐫���̂��̂ŁA���̂Ȃ�~�j�}���E�A�[�g���ɏ��̏�Ԃɍ�i���������݁A�I�ǂ̒P�ʂɂ܂Ő荏�Nj�Ԃ�������̂Ɠ������A�R���Z�v�`���A���E�A�[�g�́u�|�p�v�Ƃ������Ƃ̒�`�t�����A���́u�T�O�v���Ɍ��ɝf�v�����������炾�B������~�j�}���E�A�[�g�ƃR���Z�v�`���A���E�A�[�g�Ƃ͏�ɓ����n���Ř_���������A�܂���Ƃ��ĕ��u���ׂ����Ȃ̂ł��낤�B
�@�R���Z�v�`���A���E�A�[�g�Ƃ͂ł͂ǂ����������ł��������A�Ƃ������Ƃ���T�Ɍ�����قǂ���͐��Ղ������Ƃł͂Ȃ��������B��̂��R���Z�v�g�̂Ȃ��G�悪���݂���͂����Ȃ��̂�����A�S�Ă̍�i�̓R���Z�v�`���A���ł���Ƃ�������B���������ɈႢ��F�߂�Ƃ���Ȃ�A�u�m�v�Ƃ��Ă̗̈悪�����Ƃ������ƁA�u�v�z�v�Ƃ��Ă̌|�p�Ƃ��ĕ\���𑨂��Ă��邱�ƁA���邢�͂����������Ƃ̑F�c�ł��낤���B�܂��͂���́u�v�z�v�ł����Ĕ��p�l���ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��B�C�Y���Ƃ��đ�����Ǝ�ɂ��V�b�y�Ԃ������肻�����B���Ƃ��Ύ���������Ǝv���o���Ă��A���̕����̕��͑����L���g�U���Ă��܂��B�_�_�I�A�i�[�L�Y����f���V�����̃��f�B�E���C�h�A�����ăI�u�W�F�Ƃ������z���Ƃ��Ă��A��ؓ�ł͂����Â��Ȃ����j�I�Ȑ[���������āA�ꂵ���_������łɋ������Ă���B
�@�|�p��i�͐l�ԑ��݂������l������킯�ł͂Ȃ��A�ƌ��_�_�C�X�g�B�ɂƂ��āA����͂������́i��i�j�Ƃ��Ė]�ݓ�����̂ł͂Ȃ��A���t�Ƃ��Ă̖`���ƁA���Ƃ�G�}�Ƃ��Ȃ�������t�ɗ��ߎ���Ă����\�����@�ł����Ȃ��B���f�B�E���C�h�Ƃ������Ƃ��܂�Ƃ��댾�t�̖��ɓ˂�����B�����ċ��łȃR���Z�v�g������W���Z�t�E�R�X�X�������Ă݂�ƁA
�u���܌|�p�ł���Ƃ͌|�p�̖{������ɂ���Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B�������G��̖{������ɂ��Ă���̂Ȃ�A�|�p�̖{���������ɂ��Ă���Ƃ������ƂɂȂ炴������܂���B����|�p�Ƃ��G��i���邢�͒����j�Ƃ������̂������Ƃ�����A����ɂƂ��Ȃ��`��������Ă���̂ł��B���̗��R�́A�|�p�Ƃ������t�͑��̓I�����G��Ƃ������t�͌ʓI������ł��B�G��͈��̌|�p�Ȃ̂ł��B
���������Ȃ����G�𐧍삵�Ă���Ƃ���A���Ȃ��͂��łɌ|�p�̖{����e�F���� ����i���ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��j���ƂɂȂ�킯�ł��B�l�͂������āu�G�恁�����v�@�Ƃ������[���b�p�I�`������|�p�̖{����e�F���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��B�v�i���R�j
�G��͂����܂ŌʓI���x���ł���ƌ��A�����Ŗ��ɂ���Ă���̂́u�`�́v�ł����āu�T�O�v�ł͂Ȃ��ƌ��B�������Ő\����Ȃ����A�u�|�p�v�͑��̓I�Ȗ��Ƃ��čl����ׂ��ŁA�]���āu�T�O�v�������ň����ׂ����B���̊T�O�Ƃ͍��܂ł̊G��⒤���I�Ȍ���ł͂Ȃ��A�ʂȐ��_�I�c�ׂ̌��t�Œ�`���ׂ��ł���B���ꂪ�R�X�X�̎�|�Ǝv����B�����ɂ�����g�[�g���W�[�Ƃ����̓ǂݓ�������A�����ꂽ���e�͖����ł���B�u��ƎO�̈֎q�v�Ƃ�����̓I�ȍ�i�����Ă��A�|�p�����߂��Ă������@�_�Ƃ��ċɂ߂Ė��Ăł���B�����ɂ͈�̈֎q�̎���������A���̉��ɁA�����Ƃقړ����傫���̈֎q�̎ʐ^�ƁA��������́u�֎q�v�Ƃ�����`���Ƃ��Ċg��v�����g���A�W������B�܂�u�֎q�v���߂����Ẳ��߂̍U�h��A����͂ǂ�����ׂ����Ƃ����A��̖₢�i�l�����j���N����B
�@�ł͉��������ŋ��߂�ꂽ�̂��B�Â߂Ă����u���o����̊T�O���v�Ƃ������Ƃ��Ǝv���B���ʁi���邢�͗��́j�Ƃ�����Ԃ̊l������x����āA�|�p�A�܂萢�E�����߂��Ă������@�_�������ꂽ�̂��B���̏���Ⳃ��R���Z�v�`���A���E�A�[�g�ł������ƌ�����̂ł͂Ȃ����B
�@�Ƃ���ł��������T�O�I�ȁA�܂�͓��̒��ŕ`���ꂽ���̂́A���F�����Ƃ��ĖڂɌ����Ȃ����̂�����A��Ƃ܂�͍���B�̏����s�ǂ������N�����Ă����B�܂������Ɍo�ό����̖ʂ���l���Ă��A���i���������̂͗��ʐ��x����܂͂�������Ă��܂��B����������҃T�C�h����݂�A���o�Ƃ��Ắi���邢�͕��̂Ƃ��Ắj���p�i�i�|�p�i�j�̗~���͐�������̂ł͂Ȃ�����A�����Ƀ|�b�v�E�A�[�g���o�����A�Ђ��Ă̓R���Z�v�`���A���E�A�[�g�̐��ނ��������瑣���������ł��������B����͓��{�ɂ����Ắu���̔h�v�Ƃ��ē���ȏ�悵�Ă���̂����A���̂��Ƃ��t�I�Ɍ����Ɓu�T�O�̎��o���v�Ƃ�������B��͂�r�W���A���Ȃ��̂𗣂�ẮA�l�͑ς���̂ɐh���̂��B�܂��͖{���I�Ɏ��o�I���݂Ȃ̂��낤���B���̂��Ƃɂ��Ă͌�قǘ_�q���Ȃ���Ȃ�܂����A�����ł͐G��Ȃ����Ƃɂ���B
�@�u�T�O�v�����o�̂����Ɋ�����������V���ȍ��W���͂Ȃ����̂��B�~�j�}���E�A�[�g�̂Ƃ���ŏq�ׂ��̂����A��i���S�����Ɓi���̃G���[�V���i���ȕ������ɂ��āj���ɒu������i�ɂ݂���u���́v�Ƃ��Ă̈ӎ��ƁA�����Ō��u���̔h�v�́u���́v�ւ̈ӎ��Ƃł́A��̊J��������B�~�j�}���E�A�[�g�͎v�l���l�߁A�]���Ȃ��̂��킬���Ƃ��Ă�������ɁA���q�j�̂��Ƃ����̂�������A�R���Z�v�`���A���E�A�[�g�̐�������u���́v�͐V���Ȉ߂�g�ɂ܂Ƃ킴��Ȃ��B�u���t�v�Ƃ������݂��u���́v�ɕt������ė�������Ă����A�Ƃł������ׂ����B�������u���̔h�v���u�R���Z�v�`���A���E�A�[�g�v����͂�~�j�}���E�A�[�g�Ɠ������ߎ��l�ő��݂��Ă��邱�Ƃ͊m�����B�l�Ƃ��Ă݂�܂��u���̔h�v�Ƃ��đ������ق����������₷���B���̈�A��̍�ƂƂ��Đ��؎u�Y�A�c���M���Y�A�͌����v�A���邢�͕F�⏮�Â̊����ɂ��̓W�J���݂���B���؎u�Y�ɂ��Ėl�͈ȑO�A�����Ȋo�������������Ƃ�����i���S�j�B
�u�܂Ȃ����̎��Ӂv�i����\�N�\������������p�فj�Ƒ肵�������ɂ͌ܓ_�̑�삪���ׂ��A�͂Ă�����ǂ��������悢�̂�獢���Ă��܂����B���̎��������Ƃ́u��Ƃ̕����v�̂��Ƃł������B�u�w�^�E�}�v�Ƃ����v�l���A��X���`�ȓ��{�l�̊����ɂǂ��܂ŐH������ł��邩�s�������A���؎u�Y�́u�w�^�E�}�v�Ȃ̂��ȂƂ��v���B�ˑR�u�w�^�E�}�v�Ƃ������t���o�����̂����R���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂����A�܂��͉�Ƃ̕����̂��Ƃ���b���Ă݂����B
�@�l�̑����͑�l�Ŗ�Z�\�Z���`�����A�����P�ʂƂ��đ��ʂ��錴�n�I�ȕ��@�͂������ȊO�ɐ��m�ł���̂��B��܂������k��������݂����Ă���Ƃ������ƁA���ꂪ�������L�[�E�|�C���g�ł�����悤���B���āA��b�H��������A����x�j���A�����֊��荞�ރZ�����g�A�W���C���g�͂ǂ�����ׂ����B�₪�ē����ɓ���A�ǎ���{�[�h�A�z���H���A�K���X���̑����X�̕���������ꍞ��ł���B���������������A��������ɂ���ׂ��ʒu�ɒ蒅����B������ׂ̒��ł̈�̒������`������B�����������z�H����[���猩�Ă��āA���؎u�Y�Ɍ��ѕt����s�����������Ă��炦�A�u�ւڂȑ�H�v�Ƃ����ׂ����B�Ƃ������̓v�����f�����삪�V���Č��K����H�ɂȂ��Ă��܂����A���N�̔M�������������ɂ����܌��Ă��܂��̂��B�����ĐE�l�ł͂Ȃ��B�ہA�E�l�ɂȂ邱�Ƃ��Ӑ}�I�ɔ����Ă���B�������Ă����āu���́v�𗘗p���Ȃ���A���E�̍\���͂����ɂ���ׂ����Ƃ������Ƃ����n�߂�B�܂�́u���ʂ̌���v�Ō�낤�Ƃ����ӎ��ł���B���̎v�z�i�����j�͂ǂ����A�_���ɋA�˂������̏����̊Ԃ����܂悤�B���̑��g�Ōċz����B�����t����ꂽ���g�̑O�ƌ��ɐ݂���ꂽ�u��v������A���́u��v��ʂ��āu���́v�Ɓu���́v�Ƃ̊W�����B�����ɐ��̊j�S������悤���B�������͂�A�u���o�̊T�O���v�Ɠǂݑւ��Ă��悢�B
�@�R���Z�v�`���A���ȃX�^���X������Ă����ƂƂ��āA�͌����v�̎d���������Ă݂悤���B����\�N�Z���ɊJ�Â��ꂽ�u�����̍�Ƃ����W�v�i�_�ސ쌧���ߑ���p�َ�Áj�ɏo�i���ꂽ�����g�p������i�Q�ɁA��̋���ȃ��b�Z�[�W��������B
�����Ƃ��Ă��n���ȐF�����Ɩ��\��ȕ\�ʂɁA�ǂ�����Ɨl�X�ȍH�v���݂��Ă���B���̂قƂ�ǂ�������ŃJ�o�[���Ă���B�u�W�[ ��q�E�����̔��v�A�u�W�[��q�A�����S���v�A�u�W�[���̉����E��q�v�A�u�W�[���̉����E�y�A���A��C�v�������đ肳�ꂽ������ǂݎ�邾���ł����t�͂ǂ�ǂ�Ƒ��B���Ă����̂�������B�u���v�Ɓu��q�v�Ƃ�������Η��ɂɂ��镨������̓_�łȂ��~�߂Ă����B�����Ƀ��W�b�N�̋U��������͂��܂����B���邢�͓]���A�ϗe�ƌ��������Ă��悢�B�����ƒ��ׂ����̂��`��ɕϖe���A�������Ƃ��Ă݂Ȃ����Ƃ��痣��āA������]�ƃX�g�C�b�N�ȏ@������m�炸�m�炸�̂����Ɍ��n�߂�B�ǂ��������ɕY���Ƃ�悪��ȋ֗~��`�҂̌��炵���L����k���ł��܂��B
�͌����v�̎d���������Ă݂Ă��A���ꂾ���̌l�I������v�l�̕��@���g�U���Ă����̂��i������L����镔��������͓̂��R�����j�B�v�͏\�l�̊Ϗ҂�����Ώ\�l�̎��_��������Ƃ������Ƃ�F�߂Ă������Ƃł��낤�B��Ɂu���ʂ̌���v�Ə���������ǁA�Ⴆ���̋��ʂ̌�����̏ۂ��Ă����Ƃǂ��Ȃ�̂��B���邢�͗l�X�Ȋ�ɉf�錻�ۂ��h�N�T�Ȃ��ɁA�X�g���[�g�Ɍ��߂Ă����Ƃǂ��Ȃ�̂��B����͂�����X�L�]�t���j�[�ȎU�����������܂Ȃ��Ȃ��Ă����ł��낤�B�����A����ł悢�̂ł͂Ȃ����B�܂�I�Ȏ���Ō������Ă������ƁA���̍�Ƃ̍ĕҎ[������Ƃ������ƂȂ̂ł͂���܂����B
���̂��Ƃ𒆑�V��̓����{�[�ɊĎ��̔@���\�������i���T�j�B
�w�E�E����̓����{�[���A�A�[�g�Ƃ͑z���͂ƋL���̗͂�����Đ��E����̏��F�� �Ƃ��đn�����Ȃ����A�g�D���Ȃ����A�\�z���Ȃ������Ƃ�����̂ł���Ƃ����ߑ� �̃��}���`�B�b�N�Ȍ|�p�v�z���A�͂Ȃ��狑�₵�悤�Ƃ��Ă������߂ł���B�ނ� �z���͂ƋL���ɂ���đg�D���ꂽ���E����̂��邱�Ƃ̂ق��ɁA����ł͂Ȃ����̂ق��ɂނ��āA����I�Ȉ���ݏo���Ă��܂��Ă����B�ނɂ́A�ӂ��l�X�����E���Ƃ��������Ƃ��Ă�ł�����̂��A���������ɂ͒m�o�̎d�g�݂�z���͂� ���i�⌾��̒����Ȃǂɂ���āA���炩���߂��̉^������V�����������Ƃ߂�ꂽ�����őz���I�ȁi���e�I�ȁA�ƌ����Ă������j�����̒��ɑg�D���ꂽ���̂ł����āA����̓��A���e�B�̂Ȃ�̉ʂĂ̂悤�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��A�Ƃ킩���Ă��܂����̂��B �ނɌ����Ă����A�����āu�����銴�o�̒�������Ȃ������I�ȗ��p�v�������Ĕނ����悤�Ƃ��Ă�������̂܂܂̃��A���e�B�A����̂܂܂̐��E�Ƃ́A�z���͂ɂ���Ă܂Ƃ߂�����ꂽ�S�̐��Ȃǂł͂Ȃ��A�L���L���ƋP�����ׂȍ��Ղ��c���Ȃ���₦�ԂȂ������ƕω����N�����A�₦�ԂȂ��������Â��Ă����^���̂��̂��̂ł������B�Ƃ��낪�A�ǂ�Ȃɂ��炵�����̂ł��낤�ƁA���E���ЂƂ̒��������������F���Ƃ��đg�D���Ă悤�Ƃ��邠���鎎�݂́A���̂���̂܂܂̃��A���e�B���ώ������A�}�f�����Ă��܂��̂��B�����Ŕނ͎��Ƃ������t�̋Z�p�������āA�g�D���ꂽ���E����̂��������Ƃ����̂ł���E�E�E�x�B
�@����͌��A����ɂ��Ă��A������ɂ��搢�E�̐V���߂ł͂���̂����A�������ď����Ώ����قǁA���ꂽ��i����C�����[�W��������菜�����Ƃ̍�����͂�����Ƃ��Ă���B�͌����v�ɂ��Ă��u�|�p�v�Ƃ����g�g����蕥���ẮA���̌�鍪���������Ă��܂��Ǝv����̂��B�����ł͂Ȃ��A�|�p�Ƃ����u�R���e���g�v�����ւ��邱�Ƃ��A�`���������p���Ȃ�����V���ȑn���̌���ɏؐl�Ƃ��ė����Ƃł�����Ǝv����̂����A���̂��Ƃ͂���������̓I�Ș_�����~�����Ƃ��낾�B�l�j���܂т炩�ɂ��邱�Ƃɂ��������̒�R������̂����A���Ɂu���v�Ƃ��Ă̏؋��i��O�ɁA�u�R���e���g�̐��������v�������ɂȂ���Ă������A����Ă݂����B
���P �h�m�`�w�M�������[�u���ʐS�W�v�i���N�j
���Q �{��~�u�{��~����W�E�U�v���p�o�Ŏ�
���R �W���Z�t�E�R�X�X�u�N�w�Ȍ�̌|�p�v�A��t���v�u�~�j�}���E�A�[�g�v��葷����
���S �ْ��u�W����̕Ћ��ɂāv����o��
���T ����V��u�`�x�b�g�̃��[�c�A���g�v���肩���[
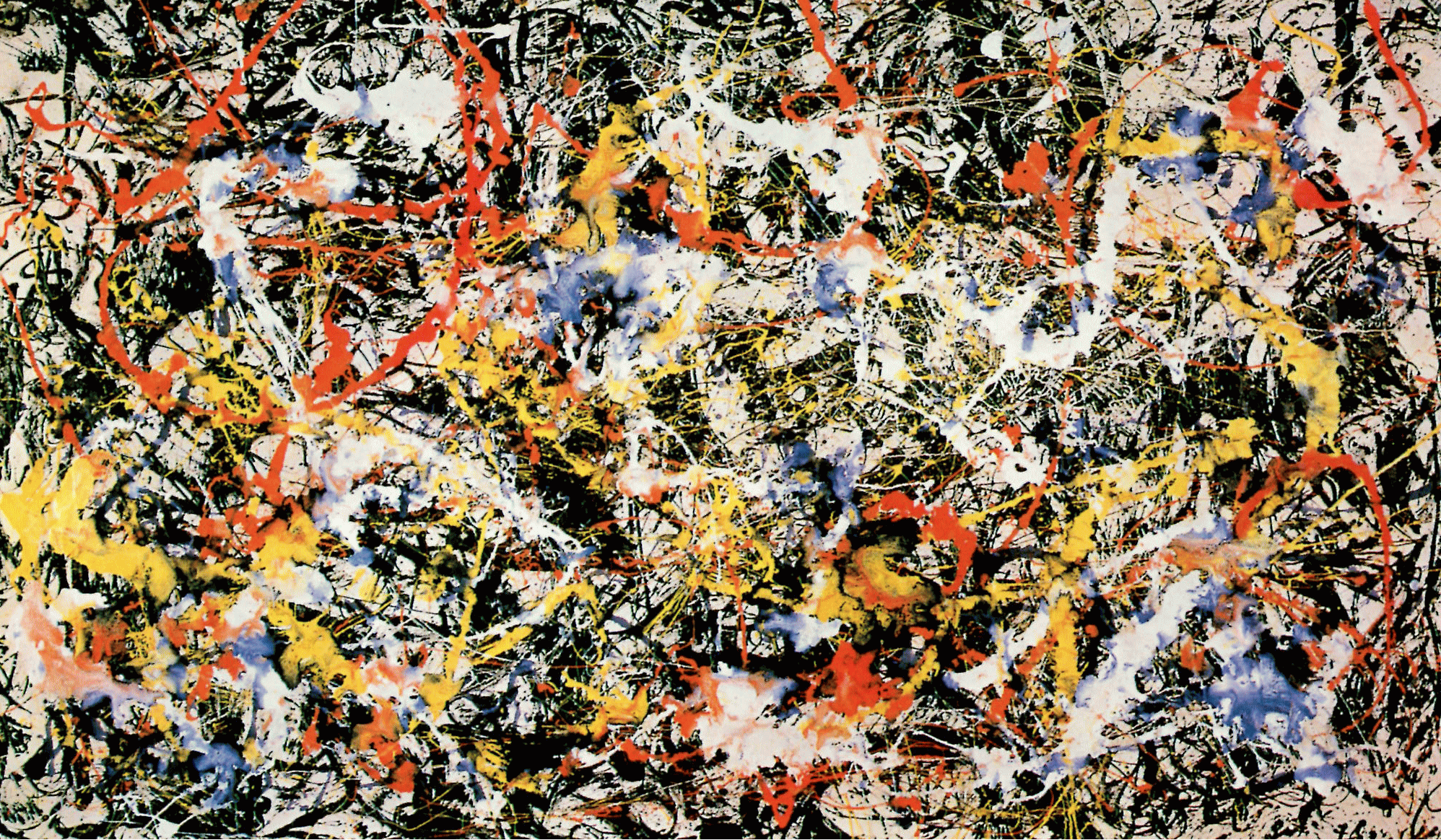 |
| �W���N�\���E�|���b�N�u���ʁE�P�O�v |
�O
�@�l�͂��̓�\�N�قǂ̊ԁA�ʼn�A��ɓ��ʼn搧������Ȃ̃C���[�W�}�̂Ƃ��čׁX�Ȃ��瑱���ė����B���̌_�@�Ƃ����A��w����̏W���u�`�ŋ��N�Y�̔ʼn�u������u�����̂����������ł������B��㎵��N�A��w�O�N�̔N�ł������Ǝv���B���݂ł͔ʼn�R�[�X���ݒu����Ă���ƕ������A�����͂܂��w���̒��ɂ͐ݒ肳��Ă��炸�A�W���u�`�Ƃ����`�Ŏ�u���邵���Ȃ������B
�@���\�N���ۓ����̔N�ɑ�w�ɓ��w�����l�ɂƂ��āA�Љ�̌����Ɣ����Ƃ��Ă̒��É��͊m���Ɉ�̓��݊G�ł������B���ƕ����ɖ�����ꂽ�w������ԎR���ŕ��Ă�������ɐ��������́A�����ɂ͖��߂邱�Ƃ��o�����ɒ��ɕ����A�e�X�̏�ǐ[���ɂ��Ă�����҂�����A����́u�푈�������v�������̂��ƁA����������Ԃ��ĕ�����̂āA�̐��̒��ɖ��U���ł��Ă������҂������B�l�͂ƌ����ǂ���ɂ��g�ł�����䩑R�ƃm���|��������A���𓊂��̂ĂĂ����悤���B�G�͕`�����������̂��ƂɑS�g��v��������ɂ́A���͂͑��R�ł���߂������A�Ǝ�Ȑ_�o������������Ȃ������B�u�x��Ă����N�v�̈����݂͉����̎���ł������ł��邩���m��Ȃ��B���ǂƈ����B�v���Ԃ����̍��́A����Ȏ���ł��������B����ΐ����̋G�߂ł��������̂����A����̔w�i���t�B�[�h�o�b�N���Ă����Ƃ��A�S�����Ƃ���ɑ����������A���邢�͘Z�\��N�̈��c�u���u����v�ɏے����ꂽ�A�J�f�~�Y���ȑ̎��ւ̌��������A���R�Ƃł͂��邯��Ǖ~����Ă����悤���B������������w�i��w�������҂��A�������ォ�牄�X�Ƃ��Čp������Ă��鋌�ԈˑR�Ƃ������ʉ搧��Ƃ������m�ɁA�����ȍm������ĂȂ������Ƃ��Ă��A�ہA���̂��Ƃ̕������R�ł��낤���A�ނ���A�J�f�~�b�N�ȓ���ے肷�邱�ƂŁA�q���C�b�N�Ȕg�ɘM��Ă��邱�Ƃ̕����A�����{���̐t�Ƃ��Ă����������B
��ꂠ����̋�C�͌����ɍ��w���Ɠ��Q�o�A������DIC�iDestruction is construction,�j���n���Ȃ�j�ƌ������t�ɏے������i�F�ɓh��ւ����Ă������A�����̓����s���p�ق́A�ٗl�ȔM�C�Ɓi����͂����ꐮ�ڂ��ꂽ�R���Z�v�`���A���ȗ���ɗ��ߎ���Ă����̂����j�A�M�C����߂邱�Ƃ̋�����Ȃ��܂��ɂ����낤���Â��������Ă����B���c���O�́u���E�l�v�́A�W���������Ɋۑ��l�{���ɂ��ăA�N�g��\�����A����G�́u�̂ڂ�v�͐l��H�����悤�ȁA����ł��Ė��m�ւ̋��|�ƌǐ⊴����݉������Ă������i���������\����{���p�W�j�B
�@�������w���^���Ƃ������̂͏��F�ӔC�̂Ȃ��^���ł�����B�}���ȉ��̌�ɁA�x���ƂȂ鉽������̃o�b�N�{�[�����v�������̂����Ƃ̐���s���Ƃ���������B�A���߂���̉��ʂ��Ȃ��}�X�����ŁA�l�͍ĂъG�搧��ɖ߂��Ă������B�A�J�f�~�b�N�̓��Ɉ����������Ă��܂����B�������n���ΗF�͎O�X�܁X�����E�o�����݂Ă������A���邢�͊w���܂��l�����邽�߂ɁA���������Ɨ��w�f�b�T�����܂�����n�߂�҂������B����͋}�ɗ₦����ŁA�������߂Ă��邱�Ƃ������̂悤�ɂ��f���Ă����B���x�@�����x���M�[����A��������{�ꓹ�搶�̃t�����h���Z�@�u�����w���͗p�ӂ���B����������̔@���ǂ��ł��������ăn�E�Y�i�[��u���E���[�A�G�����X�g�E�t�b�N�X�����́u�E�C�[�����z�I���A���Y���v���Љ���̗��s�����B�`���͂�������ׂ����A�ߑ�̊G��͐��}�ɂȂ肷���Ď��ł����A�ƁB
�@�u�E�E�E���̌ӕ��i�Y�_�J���V�E���j�̔����E�E���ێ����邱�ƁB�E�E�E�O���b�V�B�̊W�ɂ���Đ�������E�E�E����͌���`�@�i���Ɉ�۔h�Ȍ�j�Ƃ̈Ⴂ�̌���I�ȓ_�ŁE�E�E�v
�@�����́A��{�ꓹ�ɂ��t�����h���Z�@�u���Ɋւ��Ă̊o��������ǂނƁi��㎵��N�\�ꌎ�j�A�x���̂̌��S����G�̋�̍d�����Ƌ��ɁA�ÓT��@�̕K�R���ɖ�N�ƂȂ��Ă���̂��悭������B���������ɉ����̎��������������Ȃ����ʉ�̏ł�́A���̃G�l���M�[�Ƌ��ɁA�M��ɏ悹���痿���A�m���ɋ��łȌӕ��̎x���̂ɒ蒅�����邱�Ƃ̉����ɁA�g���ςˁA�]�����čs���B���������Ă̌��ʂƏH�̓�����������܂��̂悤�ɂ����āA�t�̏I��肪���Ă��Ă����ł��邩�̂悤�ɁA����͎��ɓ��R�̂��Ƃ����芷�����Ă������B�\�Ԃ̏L����Y�킹�āB�����ʼn�̃v���Z�X�����ɂ������ăt�H���[����B
�@�u�ǂ��������̂Ȃ̂��낤���A�w������̂��鎞���Ƃ������̂́B�����₢�����Ă���C���[�W�̉ۈ������̂Ȃ��ŁA���鋰�鎩�Ȃ�T���Ă����A����������������������ق̖��邢�������炷��A����͂����ɂ��Â��A��s�̖��H�q�Ղɋ߂����A���ꂱ���j�[�h���Ў�ɕ��I���ł̈Í���Ԃֈꋓ�ɂ̂߂荞��Ō��̐�Ɏd�~�߂������̐��X�A�ӂ�Ԃ�ΉE�����������Â��A����������܂炸�ɂق̂��ȑO���̋Ō��Ɍ������đ��葱���Ȃ�������Ȃ��A������������͍��́A����Ȏ�����������̂��i�ȉ����j�E�E�E�v�i��1�j
�@�����̖l�̍�i�𒆗ђ��ǐ搶�́u���R�m�E�������N�v�Ƒ肵�āA����ȕ��ɕ��͂��ĉ��������B���̐�ɍ��߂�ꂽ�t�̋ꂫ�v�����A����ɍ��ނ��Ƃɂ���ē����鉼���Ƃ��Ă̎��ݐ��B����͓����Ɂu���v�Ƃ����ϔO�̒D��ɂ��������B���̌��o�̒��ł̊m�����ɑ��āA�s�m���Ȑt�͂ɂׂ��Ȃ��������f���ē��~����B���܂���v���Ή��Ə�Ȃ��t�Ȃ̂��Ǝ��}������Ȃ��̂����A�����̂ǂ�ǂ�Ƃ��������̂��Ȃ��ɂ����āA�ʼn�̃v���Z�X�͑N�₩�Ȏ�ƂƂ��Ėڂɉf�������̂��B
�@���ۓW�Ƃ��Ă��d�v�Ȉʒu���߂Ă���u�������۔ʼn�r�G���i�[���W�v�́A���̂��Ƃ�������B�掵��W�i���\�N�j�ɏo�i�����ؑ����C�́u���݈ʒu�v�A��c�N��́u���L�v���邢�͑�\����{���p�W�i���\��N�j�ɂ�������Ấu�V���[�Y�������v�ɂ݂���A��������ʐ^���������_�̓]��ɁA���E���u���ɂ��ĒD�����Ƃ����Ӑ}���ǂ݂Ƃ��B�����̍�Ƃɒ蒅���ꂽ�v�����g��ʂ��āA�䂪����̌������ɍL��������ЂƂ̓���������C���ł������B�����Ɍ�����X�s�[�f�B�ȉ�ʏ����́A���ʂɂ͂Ȃ��V�������o�ł��邵�A����͎�ƂƂ��Ă��u���ł���B�J�����A�C��������p���y�ڂ��Ă͂�����̂́A�\���̈Ӑ}�������Ŕʼn�Z�@�Ƌ��ɍK���Ȉ�v���A�Ƃ������Ƃł��낤���B
�@�����������ʉ�̍I�k�ȋZ�@�Ƃ��Ă̐�c�A��ƁA�ʼn�Ɍ������ʏ����̃X�����Ȑg�U��́A�ꌩ�������悭�f�邵�A���o������������B���n�Ȑt�͊ȒP�ɗ��ߎ���Ă��܂��B�����̋��N�Y�͑��g�ɍ��̃V���c���ǂ������������_���ȏo�ŗ������D�u�Ƃ��Ă������A�i�������X�ɐ搶�̑̓����ނ���ł������Ƃ��m�炸�ɁE�E�E�j�A�����ȓ���ƈ،h�̔O������Ă������Ƃ��A���̂��Ƃɔ��Ԃ�������B�Ȃɂ������ʂ���̈�E��]��ł����҂ɂƂ��Ă͐�ڈ���̃`�����X�ł��������A���m�Ƃ̑����Ƃ��Ă��u�ʼn�v�͖��邢�ޗ������Ȃ�A�����ăx�g�i���̓D�^�ނ��Ƃł͖��������͂����B
�@��������͂Ƃ������Ƃ��āA�F�ʕ\���ɋɂ߂ċK�����ꂽ�Z�p�A�t�Ɍ������x�̋Z�p����������ΐF�ʕ\���̓�����ʼn�̐��E�ɁA���̂���قǂ̂߂荞��ł������̂��B
�@�u��̌��́A�S�Ă̑��������₵�Ă̂��A�݂�����̗͂ɂ���āA�Í��̐��E�ֈ�����ӂ݂����l�ԁv�i��2�j
�@�Ⴆ�����a���̂����������t�ɏے�����郂�m�N���[���ȕ��i���A�h�X�g�G�t�X�L�[�́u�n�����v�܂ők�サ�Ă������ƂŁA�ӎ��͍d��������B�����ɓ��ʼn�̔Z���ɂ��Ď����Ȉłł���[�������Ƃ炵���킹��ƁA�Ȋw�I�ȕ��͋C�ݏo���āA����ł��邱�ƁA�N�w�I�ł��邱�ƁA�Ɋ��荞��ł����B���̍������A�l�ʼn�ɓ������ꂽ�ʂ̖ʂł̌����̈�ł��������B���w�Ƃ͈�����t�B�[���h�Ō��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���A���w�ɖD������Ă����̂��A���̎���ł��������悤���B�i���̂��Ƃ�NjL����ƁA���Z����̉��t�ł�����̊��Ǖ��搶�i��せ�O�`���܁j�̕��w�ɑ���[�����w���A�z�ƂȂ��āA�������Z���ł������l�ɔ��ʂł��邪����I�ȓőf�������ĐZ�����A���̂��Ƃ���ɋ��N�Y�̕��w���̋����ʼn��i�Ɉ������܂�Ă����z�ƂȂ��Ă����Ƃ́A�����m��R�����������B���X�ɂ����m���ɕ��w����̉e�����͂�݂A�`������Ă������ƂɂȂ�B�j
�@�m���ɁA���݂܂łɖ�O�S�_���́A���i���܂߂������ǂ����O�����ɑ��s���Ă����w�i�ɂ́A���w�I���������ł͌��Ȃ����̂�����B�u�F�v�Ƃ͓��Ă��Ă����������̂Ȃ̂��낤���A���m�N���[���\���͓��Ɏn���������Ȃ��B���ꂾ���ɋZ�p�Ǝv�l����v�����Ƃ��̕\���͂ɁA�}�炸���S�̐k���𖡂���Ă����̂��낤���H�G�ꂽ���ɐ���オ�����V�����{�l�C���N�������Č�����B�����炭���ʼn����������l�Ȃ�ΒN�ł������키�ł��낤�A���[���[��ʉ߂��A�������鎞�́A���̋��̂Ƃ��߂��ɂ́A�����ȑn���ւ̔�������Ɖ����J���Ă���N�[���[�̋�Y�Ɯ��������݂��߂邱�Ƃ��ł���B���ꂪ�i���V�Y�������̍s�ׂȂ�A����ȃi���V�Y���ɓ�\�N�߂����̊ԁA������������͂����Ȃ��B�����炭�͉������ŁA�v���X��ʉ߂���Ƃ��̎v�l�̋t�]���ɁA�S���������̂��낤�B
�@�����ō������ʼn搧��ɂ��Ă̋�̓I�Ȍ��������Ă݂悤�B��w�@�ʼn�Ȃ̎����ɒ�o�������_���̒����猾�t�𒊏o���Ă݂�ƁA
�@�u���ꂩ��̌����ۑ�̊T�v�Ƃ��Ă܂��E�E�E���ʼn�̎����Ă��鍕�Ƃ����F�̔�������\�����E�E�E�C�}�[�W���̊��N��ʂ��āE�E���R��K�R�Ɋ����E�E���̂��߂ɋZ�p�̉������E�E�E�ł͎��Ȃ��m�F�����ł���A����ł悢�Ǝv���܂��v�@�i��㎵�l�N�ꌎ�j
�@���Ȃ��m�F�����Ƃ��Ă̔ʼn�T�O���������͕������A�X�^�C�����������Ȃ܂܂ɁA�����ʼn_�Ɂu���v�C���N�𗐔����A�Ђ����瓺�łɑł������邱�ƂŁu���v�Ƃ����T�O����������邱�Ƃ��ł���̂��A���������v�����݂��A������x����M�������ł��������B
�@�u�����s����Ƃ��m��ʐ��삪�������ŁA������݊O���Γޗ��̒�ɓ]�������˂Ȃ��B���C�Ɣw�����킹�̖����ɔ����o����B�����������Ɣ��藈�鋕���̔g�ɃR�������m����l�́A�����������Ђ�����ɍ�ƂƂ��Ă̑��`�ɑ��鐽�����i�����I�ǐS�Ȃ�Ă��̂łȂ��j�A���X�ɌJ��Ԃ��n���ւ̌Ŏ��A�����������̂����Ȃɒ��˕Ԃ鎞�̃C�}�[�W���ƂȂ蓾�邱�Ƃ��肤�i�����j�E�E�E�����������������Έӎ��I�Ɍ��������ۂ����p���̒��ŁA�|�p�Ƃ�����̋��ςȑ��ɕ������莩�Ȃ��������M�Ԃ��ƂɁA�s�m���ȋ��������B��������ł��ǂ��A�R�c�R�c�Ƃ��ΐi���͌������������Ă���ɈႢ�Ȃ��B�����v���Ă���B�����v����������͂胉�W�J���ȕ��ꋎ��ׂ����݂Ƃ��č݂�̂��낤�B�v�i��3�j
�@�����ɂ����Ȃ���̒E���Ƃ��Ă̋\�Ԃ̏L��������B���\��N���玵�\�l�N�ɂ����Ă̐��͂́A�S�Ăƌ����Ă����قǂɔʼn搧��ɓ�������Ă���̂����A�Z�p�̉�͂������Ȃ�ɂ������̂ł��낤�B�B���p�t�I���Ȃ���̍H�[����͂܂������u�E�E�E�����ȑO���̋Ō��Ɍ������āE�E�E�v���]�`���g�A�A�N���`���g�A���t�g�E�O�����h�A�f�B�[�v�E�G�b�`���A�l�X�ȕ��I�̒f�ʂ�����������u���ׂĕ���Ȃ����̂͂Ȃ��v�Ƃ���i���q�������W�A�啅�����A���ђ��ǂ̓����ʼn悩��h�����ꂽ�j�C�f�A�̗������X�Ƃ��Ď����B�����ɍڂ������L��`�������ł��A�_�k�����Ƃ��Ă̓��{�l�̋Εא����͂�����Ƃ��Ă���B���������Ǝ������玖���ֈړ����Ă������y�Ƃ��Ă̕n�R���B�k���ł��邱�ƁA���葱���邱�ƁA��ʂ̂��ׂĂߐs�����Ȃ���Δ[���̂����Ȃ����V�Ȑ��^�ʖڂ��B����ɏk�ݎu���Ƃ��Ă̋��ɓI�n�C�e�N�Y���ł���IC�����́E�E�E�ЂƂ܂����{�l�Ƃ������m������ȕ��ɐE�l�C���I���i�Ƃ��Ċ����Ă����̂������͂Ȃ��B
�@�ł͂��̂��ׂċt�̂��Ƃ��ׂ���ǂ��ł��낤���B�s�^�ʖځA���������A�K���A�J���o�X�ɓh��c�������炵�Ȃ����炯�o����Ă��邱�ƁB�傴���ςȃ^�b�`�B�E�E�E���̂悤�ȌX���̊G����w�E���Ă������ƂňӊO�ȓ]�������邩���m��Ȃ��B�Ⴆ�g�H�I���u���͂ǂ��ł��낤���B���邢�͔��\�N��Ƀg�����X�A�o���M�����f�B�A�Ƃ��ċr���𗁂т��C�^���A�̉�Ƃ����i�G���c�H�E�N�b�L�[�A�T���h���E�L�A�A�t�����`�F�X�R�E�N�������e�j�̕`�@�Ɍ�����y�₩�Ȑg�̂��Ȃ��A�����ďd���̂Ȃ��z���ȉ�����B
�@���˂����m��Ȃ����A��M���邢�͂��̑O��ɏo���������n��Ɍ������Ԑ����A�����Ŏ����o���Ă݂悤�B��������̋�Ԕ��w�ł���B���������̋͐}�������o�����߂̐�ΓI�Ȕw�i�Ƃ��Ė����Ă͂Ȃ�Ȃ��A����Ε\����̂̋�Ԃł���B����͐����I�Ȃ���ׂ��W��ۂB�h�炬�̂Ȃ����s���ƕ��Ղ��m�����Ă���B�Ƃ���Ńg�H�I���u���͂ǂ��Ȃ̂��B
�@�u�ӑẮA���������čō��̗D�낳�̐�[�v�i��4�j�ł��邽�߂ɁA�ނ͂Ȃɂ��̂��ׂ��Ȃ��B�ׂ������ē����o���B�@�u�E�E���̋Y��A���̋C����A���̑ӑāE�E�E�ɂԂ��Ɉ����~���B�E�E�E�s��p�����y�₩�ł��邱�Ƃ͋H�ł���E�E�ETW�̕s��p�͑S���t�ɁA�͂����߂Ȃ��B�����������Ă����B�����S���̂������ȉ�����c���Ȃ�����A�������ڂ�����Ă����B��͉Ԃ̂悤�ȐՂ��c���A�����ŁA���̐Ղ�������n�߂�E�E�E�����̊�Ղ��̂�Ȃ����A�����̉A�C�ȕs�ѐ����̂�Ȃ��B�o��������̂Ə��ł�����̂Ƃ��A�@�@������̏�Ԃ̒��Ō��т��邱�Ƃ������Ă��邩�̂悤���B�v�i��5�j
�@�͂����߂Ȃ��s��p���Ƃ͉����B����́A���邱�ƁA�ׂ����Ƃ������Ȃ�����Ă��邱�Ƃł͂���܂����B����͐�M�ɂ�����n�Ɛ}�̏j�����ꂽ�W�Ƃ͑S���Ⴄ�_�@�ł���B�n�邱�Ƃ������g�������Ē��߂�B�u�E�E���E�̑O�ɂ����A���܂��ɒP�g�Ő��E�ɏ������悤�Ƃ���A���̎��̏d�傳�ɐg���ق߁E�E�E�v�i��6�j�k����B�M����肭���ꂸ��䩑R�Ƃ�����ł��܂��B���̐k���ɑΛ����鎖�ŁA�₪�Ă͌y�₩�ȕs��p�����K���̂��B
�@���������{�̓y��Ŕ|�{���ꂽ�E�l�C���I�ȕ��y�ƁA�g�H�E���u���Ƃ̊Ԃɗ���Ă���앝�͌����ďk�܂���̂ł͂Ȃ��������B
�@������x��������ЂƂ̖ʂ��l���Ă݂悤�B���H���X�̐��ɏo������̂����̍��ł������͂����B�����₩�ȉ�ʂ���f����F���́A���i�ł��邪�䂦���`��ŁA���̃^�V�Y���͒ɁX�����B���H���X�̐l���ɂ�����u���Q�v�́A���̌��t�̎��s�v�c�Ȗ��͂ŁA��\�̖�����������邱�ƂȂǂ��₷���B�܂��̓G�����X�g�́u�X�v�A�t���b�^�[�W���̌��Ԃ���`���ߑ�̈Â��B����͋��N�Y�̍�i�u���v�ɕY���Ă��镵�͋C�Ƌ��ʂ����]�Ƃ������t�́A�ʂ̕W�L�ł���B���邢�͔ѓ��k��́u���l�̋�v�A�u�E�E�E���������A���Ă����^�n�̍�������ڂ����E�E�E�v�Ƃ������Ɍ�����A�W�X�Ƃ����꒲�̒�����˂������ꂽ�������ȋƒf��B�����̃����^���ȃt�B���^�[��ʉ߂��āA������Ƃ��Ă͌`�Ԃ�������甭�y���������Ƃ�����]���A���̏W�ςݏo���Ă������i��i�u�����́v�A���Z�N������n�߂Ƃ����A�̃G�b�`���O�j�B
�@�u�t�H�����̕ω��ƁA�����ɕ\�����ꂽ���ƈÂƂ̔����Ȑ��E�A�����ɋA��̂ł͂Ȃ����Ƒz�������B�����Ƃ͈�{��{����ł������Ƃɂ���Ď��Ԃ�E�ݎ��A���邢�͓��ݎ�邱�ƂȂ̂��낤���B���̎��ԓI�Ȍo�߂�łɕ������邱�Ƃɂ���āA�Ђ���Ƃ���ƁA�����̕\�����@�Ȃ�A���Ȃ̎��݊����������邱�Ƃ��ł��邩���m��Ȃ��B�ςݏd�˂�ꂽ���ӎ��Ȑ��͂����āA��̃t�H�������`���B�����ɋL�����ꂽ�`�͂��łɈ��鐫�i���咣���n�߂�Ǝv����B�����͎̂v�z�ł͂Ȃ��B��̌����ɕ\�L���ꂽ���̂ł���B�������u���́v�́u���́v�Ƃ��āA�����������Ƃɂ�莩���ƕϖe����B�����ɍ��߂�ꂽ���邢�͕������߂悤�ƈӎ����ꂽ���́A��Ƃ̎v�l�֒������A���X�̍�Ƃ̈ӎv�����n�߂邾�낤�B�v�i��7�j
�@���]���f�[�g�邱�Ƃ̕s�\���͊��ɂ��Ċm�����ꂽ�_�ł��邩���m��Ȃ����A����Ȃ��̂��Ƃ��Ă����X���ɂȂ�̂��H����ȃ��W����������B�����̂��v�z�Ɗ����Ă��Ȃ��D�݂��B�ߋ��ɏq�ׂ�����Ă������Ƃ̏����Ԃ��B���N�Y�̎v�O�̎P���A���Ȃ̞B�����ɋC�t���Ă��Ȃ��t�قȍl�������A���̍����班�����v�l�������o���Ă����悤���B�G�������g�Ƃ��Ă̓_�E���E�ʂɏW�ꂽ�������u��`�v�Ƃ������t���o���A��������n�܂��{�\���ɉ����o����Ă����Ƃ��A�͂��Ȃ�������m���n�߂��B�G���O���[�r���O�Z�@���K�����Ă������ł��낤�B���ɑ���v������͂���Ȃ�ɔM�������悤���B���\�N�ɏo�i�������[���h�E�v�����g�E�V�i�T���t�����V�X�R�j�ɊāA�f�ނ̒�R�����q�ׁA�Z�p�ߏ�ɂ�镾�Q��r�����邽�߈ӎ��I�ɍ\�����咣���悤�Ƃ��Ă���B�m���ɓ��ʼn�Ƃ��������̏o�������琶����Z�p�̖v���Ԃ́A���߂��ڂŌ������ƕs�C���Ȃ��̂��B������߂��z������U��Ԃ���������͂����ɂ͂Ȃ��A���������̃U���U���Ƃ������������オ��B�G�̎������͉�ʂْ̋����ɂ���̂ł����āA�ɖ��ȃe�N�l�[�̌J��Ԃ���鏊�ɂ��낤�͂����Ȃ��B�ł���Ȃ�A��蕁�Չ����ꂽ�`����Ƃ��Ă����ׂ��ł���B�Ⴆ���̂��Ƃ�쑺���́A
�@�u�����̍�i�͐F���`���n���ŁA�i�ʂȂ��Ƃ͉����Ȃ��B�ɂ�������炸��{��{���荞�܂ꂽ���̗��t�H���������Ղɒ蒅�����A���̍�i�ɂ����āA��邬�Ȃ��s�v�c�Ȑ����͂����Ă���E�E�E�v�i��8�j
�@�Əq�ׂĂ���B�������`�݂̂�k�y���Ă����������̕��Չ��́A��͂��ʂ̊ɖ����ɕ����߂��Ă��܂��Ƃ������Ɠ����ɋC�t���Ă��Ȃ��B�������Ȃ��Ƃ��������I��O�̐��E���甲���������Ƃ��Ă���p�͖��m�ł���A�G��̗v�f���@���Ȃ���̂��Ƃ������ȂƔF���ɂ͂Ȃ蓾���悤���B�M���̂����ނ��܂܂ɐU�艺�낷�O�q�͂����܂��҂炾���A���Ⓘ�Â̎��ł���B���������c�@�C�g�K�C�X�g���������ċz������Ȃ��B
�@�ł�}�̂Ƃ���A�Ƃ������Ƃ��l���Ă݂悤�B���]�����v���Z�X���o�āA���߂Ĕʼn�Ƃ��Đ�������Ƃ������ƁB�C���[�W�̌@��N�����̌�ɁA����Ȃ�|����v������邱�ƁB���̗����̂������ސ_�o��p�ӂ��Ă���Ƒ�����������A�ڐ��̋�����Ƃ��B�l�͂��̂���A�]���ăv���Z�X���������ƌv�悵���̌v��ɑ����Ď葱�������������Ƃ����A����̏I���Ǝv���Ă����B�܂�C���[�W�̐�s�͕K�{�����ł���A���̐����͑�������̏���������d�v�ȃ|�C���g�ł������B�c���ꂽ�ۑ�Ƃ�����Ɛ��̖��A����������匚�z�v���W�F�N�g���D������A�فX�Ƃ��ēz��̔@����Ɛ��s����l�v�̊m�ۂ݂̂ł���Ǝv���Ă����B�v����Ɂu��Ɛ��v���̂��̂̂Ȃ��ɂ͑債�����n���Ȃ��ƁA�����������Ă����̂��낤�B
�@�������\�����ꂽ�`�i��i�j�́A�s�v�c�ȁu��炬�v��\�o���Ă����B�������I�v�e�B�J���ȁu�͂ݏo���v�����o�̂��������������x�͌v�Z�ɓ���Ă������A���҂����m���������B��������́u���o�̂�������v���Ȃ��͈͂ŋ�����邱�Ƃł���B�u��Ɓv���̂��̂̒����甇���o�Ă���u��炬�v�������̌v����đ��B���A�]��Ƃ��Ĕ���������̂Ƃ��ẮA�����Ɏ�ɗ]����̂ɂȂ��Ă��܂����̂��B�U��Ԃ��Ă݂�Ƃ��̂��Ƃ́A�u�����v�Ƃ����A���`�����Ɍg���҂��܂����ɍl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�������Î����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�������M��Ă���҂̊�ɂ����������Ƃ��f�낤�͂����Ȃ��B���邢�͂��́u�h��������́v�������Đ�̂Ă邱�Ƃ�����Ȃ̂��ƁA�����Ⴆ�Ă����̂�������Ȃ��B���̂��Ƃ��R�{�a�O�̓~�j�}���Y����_�����̂悤�ɏq�ׂ��B
�@�u�E�E�E�����炭�~�j�}���Y���́A��҂Ƃ��������A�������Ȃǐl�Ԃ̗v�f���ɗ͔r���邱�Ƃɂ���āA���ՓI�Ɏ�������|�p��ڎw�����B����̗\���m�����Ȃ��ɍ�i���̂Ɍ��������Ƃɂ���Ă̂ݍ�i�̊ӏ܂���������|�p��ڎw�����̂�������Ȃ��B�@�����A��i�����ݏo�����Ɏ���v�l�̃v���Z�X��ǂݎ�邱�ƂȂ��ɂ͂�͂��i�̊ӏ܂����藧���Ȃ��B���Ȃ킿��i�����̉ߒ��Ƃ���������r�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃ��~�j�}���Y���ׂ̊������H�ł͂Ȃ������̂��낤���E�E�E�v�i��9�j
�@�R�{�̘_�q�ɂ��Ă������̃A�W�A���p�ւ̃A�v���[�`�ɂ��Ă��A�v�͂��̕��y��`������Ă������j���ɂ��Đ������邱�Ƃ�����Ƃ����A�ɓ�����O�̎������q�ׂĂ���ɉ߂��Ȃ��̂����A�u������O�v�Ƃ������̂��p�ӂ�����v���Ȃ��Ȃ����������݂Ȃ̂ł��낤�B���邢�͂�����������B�Ⴆ�Ε��J�s�l�́A
�@�u���яG�Y�̍�i�����͓ǂނ��Ƃ��ł��Ȃ��B�ނ̍�i�͊Ǘ�����Ă���B�����ɂ͂�����̎�肵���Ȃ��B�ނ̌��t�͂����]�v�Ȃ��̂��������Ƃ��āA�i���Ȃ���̂ɂȂ낤�Ɛg�\���Ă���B�������A�ނ��������Ƃ��]�v�Ȃ��̂��ނ���d�v�Ȃ̂��v�i��10�j
�@�ƌ��B�����ɂ͕��w����p�Ƃ����W���������z�����A�n�삷��҂̎�����{���I�ȉ���������Ă��͂��܂����B�����ɂ������ė]�蕪�̐�̂Ă��e�[�}�ɂ��Ă������炢���������̂��B���̍����Ⴆ�������܂Ōp������Ă����Ƃ���Ȃ�A���Ɩc��Ȗ��ʂ𓊂��̂ĂĂ������Ƃ��B������������ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ɋ�łȍ����Ⴆ�ł���悤�����A���������葱���܂Ȃ���ΐi�W���Ȃ��̂Ȃ�Γ��݂����悤�B������ׂ���ɂ��������ς��ꂽ�c�y�̎R���瓾������̂�����͂����B�����Ⴆ�͂���Ƃ��āA�u��Ɓv���u�����v���̊ԂɕY�����̂�����A���ꂪ��̉��Ȃ̂��肩�ł͂Ȃ����݂邱�Ƃ͊m���ŁA�Ȃ���̕��V���̐��̂�\�����ƂŁA���ւ̃X�e�b�v�����ނ��Ƃ��ł��������B
�@���Ƃ��u�R���e���g�̐��������v���@���ɂȂ��ꂽ���Ƃ������Ƃm�ɘ_�q�ł����Ƃ͎v���Ă��Ȃ����A����̗����H�邱�Ƃɂ���ė������ꂽ�V���ȋ^�O�������邱�ƂŁA�_�|������ɂȂ��Ă������B
��1�@����ʼn�Z���^�[�j���[�X�AVol�A1�ANo,7�B��㎵�ܔN
��2�@�����a�ȁu�߂̊�v�V������
��3�@���Îs�����Z���k��u����v�攪���A���O�N
��4�@�������E�o���g�u���p�_�W�v�݂������[
��5�@�O�f��
��6�@�ΐ��k�u�M�G�̍\���v�������[
��7�@�����N�����\�����̓��L���
��8�@��\����_�ސ쌧���p�W�J�^���O���
��9�@�R�{�a�O�u�����A�g���G�vNo747
��10 ���J�s�l�u�_�C�����[�O�E1�v��O������
 |
| �������@���ʼn�u�n���ށv1975�N |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �l
�@�u���E���p�[�X�y�N�e�B�u���������Ƃ��A��X�͎U�킷��B�ނ��덕�A�������L�� �ȍ��A���ȏ�ɖL���ȐF�ʂ�{���B�v�i���P�j
���ł����͔������Ǝv�����A������F�ʂ̒��œƂ�W�R�Ɨ����Ă���B���̂��Ƃ̎����͕ς��Ȃ��B�Ȃ�Ή��̂��̔��w�i���͔������j�ɏI�n��ђ^�M�ł��Ȃ������̂��B���̗��R��₦�A���ȏ�ɖL���ȐF�ʂ��ʂ����Ă���̂��Ƃ������Ƃւ̕s����ł�A���邢�͕s�M�̉萶��������������Ȃ̂��B�����Ă��܈�̑f�p�ȋ^��ɂ������Ȃ���Ȃ�܂��B����͔ʼn�̊ԐړI�ȋZ�p�Ǝv�l���@�Ɋւ���^��ł���B���̔ʼn��}��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B���̕K�R���ɓ������Ȃ���A�łɌŎ����邱�Ƃ̍���������Ă��܂��B���ł��邱�Ƃւ̑����ƁA�ꉞ�͂����Ă݂��Ƃ���ŏ��F����܂ł��B�����̜ɂ��Ɛk�����������̎܌��ɑ�����Ė����ō���Ă��������̓�E�O�N�͕ʂƂ��āA���̂��Ƃ͂������S�̉��ɂ����Ԃ��Ă������ł���B�v�l�̋t�]���Ƃ͌������̂́A���炩���ߌv��ꂽ�h���}�ɁA�V�N�ȝ������ɂȂ��Ă����B����͔łɑ���^�`�Ƃ������́A�ނ��뎩�Ȃ̓���������n�߂��؋��Ƃ����ׂ����B���t�̏��X�����͓�x�Ɩ߂��Ă͗��Ȃ��B�܂莩���̑n��͂��V�����Ƃ������Ƃ��H�������L���Ɏ������ʂẮu�V���v�ł͌����ĂȂ��A��̂܂܂ɗ����͂�Ă����S�߂Ȃ���Ƃ��āE�E������������Ȃ��B���Ƃ����Ȃ���Ƃ����ő��ƁA�����Ɩق��Č͂�ʂĂ�ɔC���悤�Ƃ������O�Ƃ��j�R���Ă���B������ɂ������đ卷�͂Ȃ�����Ȃ����B�������~������B���������̂ɔ��_�͋P�����낤���B���Ƃ��P���Ȃ��Ƃ��A����s���邱�Ƃŏł�̋C������Â߂����邱�Ƃ͏o���邾�낤�A���₻��Ȃ��͈̂ꎞ�����̃S�}�J�V�ł����Ȃ��E�E�������v���������v���B�h��ɗh��Ă����̂��낤�B�Ȃ�Ƃ����Ȏ����������������Ƃ�������Ȏv���������ɂ��ݏo�āA���̎v���݂̂őӑȂŖ��ׂȖ��������z���Ă����B���z���Ă����H�{���ɂ����ł��낤���B�������������Ŗl�̐l���ɏA���ĉ]�X���鎞�Ԃ͂Ȃ��B����������邱�Ƃ͋�����ꂽ�ߋ���ے肵�Ă����猚�ݓI�Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ���Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�Ƃ���Ō��݂𑣐i����Ƃ������Ƃ͏n�������s�s�����̒��łǂ�ȈӖ��������Ă���̂��낤�B���Ƃ��Ζl�炪�������Ă����Ƃ������ƁA����͋ɘ_��������Ȃ������ꂾ���Ŋ������������N�����Ă���B���݂͐V���ȕ����ݏo���Ă������ƂɌq����A���ʂƂ��Ă̑e��S�~�Y����B�܂�l�����������̂́A���݂��~�߂�������l��̐l�����n�܂�Ƃ����Ȃ�A������܂�����Ŏc���Ȏ���ł���Ƃ������Ƃ��B���H�ł��邱�ƂƂ����A�ׁX�Ƃ�������̓��X�ɑ����������C���������낤���ĉ������邱�ƈʂł����Ȃ��B
��\��N�̎��A������H�L�^�Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă������k�̔ʼn�W�́u���Ƃ����v�ɁA�����Ƃ����Ȃ��O�`��l�͂��ڂ��Ă��܂������A���̍��ɂ͊��ɔʼn搧��ւ̔M�ӂ������Ă��邱�Ƃ��f����B����͂���Ȃӂ��ł���B�����������S�����ڂ��Ă����B
�u���t�ł���ȏ�A�ǂ����ł��̍������Ђ����������Ă������A�Ƃ����u��v�������Ƃ��A�Y�ꂽ���Ȃ����̂��B �\��N�ڂ̂���Ƃ��āA���N�����k���ʼn�W�����I���A����Ƃ���ŋ���ڂɂ�
�����B������������A���̂��ƂɏI��肪����悤�ɁA��������߂Â����̂�������Ȃ��B���܂͉���ǂ��������ȁA�Ƃ������S�ƁA�����ł��葱���邽�߂ɂ́A��
�̌[�֊��������͌������܂��A�Ǝv���������̋C���������G�ɓ��荬�����Ă���B
��㎵�Z�N�A���N�\�Z�Ŗv�������ʼn�Ƌ��N�Y�͐��O�A�u�d���͂��Ă��܂����H�v�Ƃ��u���݂��ǂ��d�������������̂ł��ˁv�Ƃ��������ŁA�w���̎��B�ɂ悭�b���|���ĉ����������̂��B�ʼn�ƂƂ��Ĕs�풼��A�a���̔@���o�ꂵ�A�����������ʼn搧����J�n���ꂽ�B�܂��������{�̔ʼn�E�̑��n���ɎW�R�ƋP���Ɛт��c���ꂽ���ł���B
����҂Ƃ��Ă������|�p��w�ɁA����ȑO�ɂ͂Ȃ������ʼn�̍u����ݗ�����A���܂��̌�y���w������Ă����B������̑��B���瓯�����I�ȉ�b��Ղ����Ƃ������Ƃ��A�ǂꂾ���̗�݂ɂȂ������Ƃ��B�|��̋����Ƃ����v�E�ɂ���Ȃ���A����ƂƂ��Ă�������ۂ��A�����̂��Ƃ����B�w���ɂ������]�܂ꂽ�B���t�ł���O�ɍ�Ƃł��邱�Ƃ�Y��܂��Ƃ��錵�����p���ɂ́A��əz�ƒ���l�߂�����������𐁂��Ă������̂��B
�����Č����Γ��ʼn�́A���̐t����́u�V���g�������E���g���h�����N�v�A�f�r�̂��Ȃ��ɂ����Č|�p�Ɛl���ɂ��Ă̌O���������Ƃ̂ł����A�����킵�����肽
���悤�u�Ƃ��Ă����v�̎v���o�Ȃ̂�������Ȃ��B�����Ă�����q���~�߂�B��̂��̂��A���ݎ����ł͐���𒆒f�����A���k�̉�W�������M���x�����c��ł������̂��낤���B���Ӗ��Ŗ��ʂȂ��Ƃ����H���邱�Ƃ̑����`���������̂��Ǝv�����̂́A������x����A���邢�͌�뉟������u�����v�����炢�ł��Ă��܂����B�u�����v�Ƃ͖{���ɉ��Ȃ̂��낤�B���̃G�i�W�[�̏�����������Ȃ����A���k�̎��I�ω���������Ȃ��B���������I�ω��Ƃ����ɂ͎��͖����Ⴗ���邵�A�����v���������Ȃ��B���Ԃ�A�����ƁA���̌[�֗͂����ނ����ƁA�����������Ƃ��낤�B�v
�����ȈӖ��ł����ł���Əq�ׂ�ɂ��Ă͏�������A�܂�͔ł𒇉�ɗ��Ă�K�R���������Ȃ����Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�����܂����̓�������ł��낤���A���݂ɉ��āu���v�łȂ���Ȃ�Ȃ���ł͂Ȃ����A�����ĊԐړI�ȃv���Z�X��K�v�Ƃ����Ԃɒu����Ă����Ȃ��B���ł��邱�Ƃ̑����A�ł͂Ȃ��A�������������S�̂ւ̎v�l�Ɏ��_���ړ����Ă����Ƃ����ׂ����B�_�ł���A���ł���A�����č��ł��邱�Ƃ��瑝�B���āA�����̕����Ɏx����ꂽ�S�̂������o���B���ǁA�ł�ʂ��āi����͂������A�ʼn�Ƃ������݂������������E����ɕ����Ă���Ƃ����ӎ����x�[�X�ɂ��Ă�����̂́j�l�͂����i�������݁j�ɓ��邽�߂̃f�b�T�������Ă����l�Ɏv���Ă���̂��B�Ŏ����邱�Ƃ���蕥���Ă݂�A���̂ق��_���͒P���Ȃ��ƂƂ��Č����Ă���B�������͑�Ȃ��Ƃ����A��̉�����\�z�������ɂ�����^���Ă݂邱�Ƃ̍�������m�̏�ŁA�c��Ȗ��H�̊C���ɕ��荞�܂�邱�Ƃ̐h���ɑς�����̂Ȃ�A���ɑł����Ă�ꂽ�X�^�C�����̂Ă�̂��ǂ����Ƃ��B��i�u�~�̌��v�i�M�������[�I�J�x�ł̓�l�W�A�����N�j�ɂ���āu���v���A���邢�́u�`�ԁv���������E���̂ĂĂ������B�łւ̊m�������������Z���Ă݂�Ȃ�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�ł��_���Ȃ���ʉ�ւƂ����Z���I�Ȑ�c�A���e�F���Ă����ł͂Ȃ��A�ЂƂ�̍�ƂƂ��č����I�\���̗̈�͂����Ɛ[���L���͂��Ȃ̂��B������������R�����ĕs�v�c�͂Ȃ����A����������ƃJ�I�X�̉Q�Ɋ������܂�Ă���ׂ��Ȃ̂��B����ȋC�����ł������N�̖��ʉ搧���W�J���Ă����B
�`�����Ƃ̂��Ȃ₩�ȕM�G�B��R�̉�ł��������ʼn�̂���ɔ�r���āA���Ƃ̂т₩�Ȃ̂��낤���B���̎��l�͋v���Ԃ�ɁA�����g���l�������悤�ȁA�u�₩�ȕ��������Ă����悤���B����́u���v�Ƃ�������ȃ|���^�[�K�C�X�g���쒀��������Ȃ̂��B�Ƃ��������A���炭�Y��Ă������G���S��B�\���ɂ�����f�ނ̂��߂銄���͖l�炪�l���Ă���ȏ�ɑ傫�Ȃ��̂�����悤���B�u�E�E�u�M�I�v�̐�����ꂪ������̐g�́A�w����킸�����Z���`����ĊԐډ����Ă��邾���̂��Ƃ��\�o�̏�ł͌���I�Ȃ��Ɓv�i���Q�j�ƂȂ鎞�A�����Ɍ������R����������̂��m���ɂ���B�f�ނɂ�����M�G�̒�R���́A�ĊO�ƈӎ����`������L�[�|�C���g�Ȃ̂�������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�j�[�h���ւ̈��͂��A���ʼn搧��ɂ����邠�������֗~�I�ȑm���̐����̂��Ƃ����������Ȃɉʂ����A�����Ď�������H�ɒǂ�����ł��������炾�B���������������ʉ�̃h���h���Ƃ��Č����̂��Â炢�̎��A���܂ł��I�����������A�u���f�ɓB�ł��G������Ɏc��Ȃ����Ƃɑ���������A���ׂĂ̎��̎n�܂�ł͂Ȃ��������B���̃g�[�g���W�[�͂����������ł������ɂ��Ȃ��B�c�O�Ȃ��玩�Ɠ����������N�����Đi�ނ������@����������Ȃ��̂��B�����č��̂Ƃ��낻��ł��ǂ��Ǝv���Ă���B
���ʉ�͂��Ƃ��ƁA�ƌ������A�����ăO���[�o���ɗނ������A���̖ړI�Ƃ��đn���T�������ɐ����Č���Ă݂�A�����ɂ͂��܂ł��I�����u�����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��{���Ƃ��Ă���B�u���ĂȂ��v�̂ł͂Ȃ��u�����Ȃ��v�Ƃ����\���Ԃ̂����Ɋm�łƂ�����̐��������ɔ����ł���ł��낤�B��Ɏ��Ɠ����Ƃ���������ǂ��̓��e�͖��邢�B�Ȃ����������������������������킹���ރL���p�V�e�B���A�s�����ȍ������o��ЂƂ̕��@�i�����E�I�u�E�f���j�ł�����B
���R�ł��邱�ƁA�܂�����������ŏ��ɐ����Ă݂����B�����ă^�u���E���[�T�̏�Ԃł��̂����A�l���邱�ƁB���z�ɂ����āA�Z�p�ɂ����āB���̂��Ƃ�O���ɂ����Ďd���Ɏ�肩����B�d���Ƃ́A�܂�͗]���Ȃ��̂��̂ĂĂ����A��G���������ւƉ����Ԃ��āA�g�y�ɂȂ��Ă������Ƃ��낤�B�햌������Ă�����Ƃ�ʂ��Č����Ă�����̂�����B
�Ƃ���Ől��������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��B�m���ɔɐB���Ă����G���B���̐l�̐��������j�ɂ͕K���Ƃ����Ă悢�����炩�́A��������ƍ������낷���̂�����͂����B���Ɍ��Ă��܂�����ȑO�̌����Ȃ��O�Ƃ͈Ⴄ�B�����ɂ̓^�u���E���[�T�̂����錄�͂Ȃ��B������^�u���E���[�T�Ƃ������͍̂ŏ��̈ꌂ�Ɏ��Ă���B�����Ĕ����̏�Ԃ͒��������Ȃ��B���Ȃ��ǂ��납��u�̑��݂ł����Ȃ��̂��B�܂�^�u���E���[�T�ł͂Ȃ��A���������f�W���E�r���������Ɏ�菜���Ă������A���̍�Ƃ̂Ȃ��ɉ����̎�������������Ă���̂��B���̘_�̍ŏ��ɖ߂��āu���v�ɑ���_�l��U��Ԃ��Ă݂Ă��A���X�Ɨ�������p����Ă������̂��ɂ�݂A�������G�������蕥�����Ƃɂ���ď㏸���Ă�����p������A���������A���r�o�����g�ȑΊT�O�̂����Ƀ_�C�i�~�b�N�Ȍ|�p�Փ��̐��܂��f�n���`�������̂ł͂Ȃ��낤���B�㏸��p�̎����͂��Ȃ킿�|�p������������������B�����ւ���Ɛ��������Ԃ������̕��A�㏸��p�ɊҌ������ʂ������Ă����Ƃ������Ƃ��B�l���������Ȃ���Ό|�p���܂����܂�Ȃ��B���̂��Ƃ���K�݂ǂ�͎��̂悤�Ɍ����Ă���B
�u�E�E�E�܂�A�|�p�͎q���ɂ͂킩��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B�|�p�Ƃ͐l���̌o���ł���A����ł���A�܂����]�Ɣ߈��ł���B��Ђ̊G�ɂ��A�l�����l�܂��Ă���B�l�����Ă��Ȃ����̂ɁA�G���킩��킯�͂Ȃ��B��������҂ł��A������x�͂킩��B�������A�{���ɐ[���킩��̂́A���łɐ������l�X�ł���B�v�i���R�j
�����ł͂������������ύڕ��̗ʂŌ|�p�̐[���𐄂��v���Ă���悤�Ɍ�����B��������͌���I�ȊԈႢ�ł���B���ɐ����Ă��܂����A�����ɂ���͐ϕ�����������������Ă����Ƃ������ƁA���ꂪ�|�p�����̎���ł���A�{���ɂ킩��Ƃ������ƂȂ̂��B
�Ƃ܂�A�u�킩��v�Ƃ������Ƃ̒��Ɋ܂܂�邠���̃y�V�~�Y���ƃf�B�X�y�A�͒ʒꂷ��B���H�̊C���͌���Ȃ������A����ނƂ��m��Ȃ��Q�����ɂ����Ȃ܂�A��d���_�̎v���ŐV���ȃC���[�W�̓�����҂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������̓����͂ق�̈�u�ԁA������ɂ����s�\�Ȃ̂�������Ȃ��̂��B
���s����̘A���ł������B���̂悤�Ȏ��Ԃ��ǂ������Ӗ������̂��A���݂̖l�ɂ͕�����Ȃ��B�삯���ł��蔲��������ł����ꂾ���̍��ׂ̗l����悵�Ă��܂����B�����������ő�Ȃ̂́A�Ɨv�Ă�����͂��܂�d�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B����l�͂���l�ł��ׂĔF�߂Ă��������Ȃ����낤�B���������������Ԃ������̂��H�ӎ��͌p�������Ƃ������Ƃ��ӂ݂�A��������ȂÂ�����Ȃ��B����̓��@���ǂ��ɋ��߂�̂��H����Ƃ���قnj������悤�ɁA�҂����肪�Ȃ��̂��B�G�̋�Ƃ��������̎��o���ɂ�����₢�l�߂�ׂ��������̗v�f�Ƃ́A�����đS�̂̉����Ƃ͔@���ɂ���ׂ����A���邢�͂��͂�I����҂���Ȃ̂��H�����������ׂ��܂������₩�ȗ����̑��ł���B
���āA�����N�t�A���F�X�����Ƃ̔ʼn��l�W���M�������[�I�J�x�ŊJ�Â������ɏo�i������i���u�~�̌��v�V���[�Y�ł������B����Ȍ�ʼn搧��𒆒f���Ă���B���̍����玩�Ȃ̌��݈ʒu�����Ȃ�������Ȃ��Ă����悤���B�s���l�܂�Ƃ������́A����ƌ����ׂ����B��������ɖ��ʉ��M�юn�߂��̂����̍��ł���B����͌����ĉ�����ɂȂ�����̂ł͂Ȃ��������A���܂܂ŏ����Ă����悤�ɉ��炩�̕���ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�Ȃɂ����J�������������B
�J�I�X�̔���ɕ����Ԃ��̂�����B�ڂ���ƌ����B�ꂵ�Ă���B���������G�ؗт̂Ȃ����烆�������Ɨ���������́A���ꂪ�A�E���Ȃ̂�������Ȃ�����ǁA�Ƃ�������������~�߂�B���������s�ׂ��o�āA����`�ԂƐF�ʂ�������Ɉ����邱�ƁB����Ȃӂ��ɂ��Ă������N�������̖��ʉ������Ă����B
�u����\���Ӑ}������A�����]�������Ƃ�\���s�ׂƂ���Ȃ�A���s�ׂ� ����B�^���߂��v���ԂƂ������̂�����Ƃ��āA���̂Ȃ��ŁA�ӎ��̗����͌`�Ԃ̕ϓ]�������炳�܂ɔF�߂�B�^���������ʂ̑O�ƌ��ɕY�����̂��ꌂ�ɒD�����X�������O�ȍ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�^�G�̋�Ƃ����������݂�ׂ��ʒu�ɒu�������A�s���Ȃ��̂����Ȃ炵�߁A���Ƃ��Ă̊G��ɕs���Ȃ��̂���荞�ށB
�^�\���̍���͍���Ƃ��ė��̂܂ܕ��u���邱�ƁB�������ĕ\���ꂽ�`���ʂ����ĉ������̂��A�Ԃł���̂��A�X�ł���̂��́A�܂��ʂ̖��ł���B�^��킭�Ηl�X�Ȏ�����@������A�S�̂̍\�z�ɓ��铹��������������Ǝv���B�v
��\�N�̏H�ɖl�͖��ʉ�Ƃ��ċv���Ԃ�̌W���J�����i������[�Z���^�[�E�|�C���g��\�N�\�ꌎ�j�B�ȏ�͂��̎��̊o���ł���B���������`���s�ׂ̂��Ƃ���m�߂����c�悪�A���̎��̌W�ɂ�����u�u���ƓW���v�Ƃ����^�C�g����y�o�����B�����Ƃ��Ă͖����̂Ȃ����R�ȃe�[�}�ł͂������̂��B���Ɉӎ������킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ė��ӎ��Ȃ��̂ł��Ȃ��B���̒��Ԃɂ���u�����Ƃ��Ă����ԂƂł������ׂ����̂��N�o���āA�\���s�ׂɂȂ����Ă��������̂��B
���Ƃ��Ύ��R�E�Ƃ������t�������Ɏ����o�����ƂŘb��i�߂�Ȃ�A�����Ƌ�̐���ттĂ���B�ЂƂ̕��i������Ƃ��āA��������o�Ɏ�����邱�Ƃ��瓮���o���v�l�́A�ɂ߂Đ����I�ȕ��@�_���B����Ƃ������Ƃ̊�{�̈�Ƃ��āA��X�̊�̌��萫�������ɂ���B�Ƃ肠�����͋��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��������͂���ȏ��͂ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B�܂�͌����Ȃ����E�͏��F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�������X�̎���͌��肳��邱�Ƃ���n�܂�B�������Ɋ�ɉf������̂���_�Ƃ��A���̏����t���C�ɂ����ăG�������g�𒊏o���A����Ɏ�̑���̌�A���炽�Ɍl�Ƃ��Ă̎����ōč\������B�G�搧��Ƃ͂܂肱�̂��Ƃ̈��ł�����B���̘_�̍ŏ��Ƀ��l�̊G����������ǁA���l�ɂ��Ă����̃X�e�b�v��ł��邵�A����ǂ��납�G��̉����i����Ȃ��̂�����Ƃ��āj��˂��i��ł����B�ӔN�̌���u���@�v�ɂ����Ă���𖾗Ăɏؖ����Ă��ꂽ�B���̂��Ƃ����l�����Ē��ۊG��̂Ƃ����ɗ���Ƃƌ����鏊�Ȃł�����̂����A�c�O�Ȃ��炻��ȏ�̂��Ƃ�����Ă͂���Ȃ��B�u�����ɉ�Ƃ�����ŋÂ߁v�Ă���݂̂��B䩑R�Ɨ����������l�I
�����ŒJ�숭�̘_�������Ђ��Ƃ��Ă݂悤�B�ނ́u�|�p���߂��錾�t�v�Ƃ������_�ŁA���X�L���́u�G��̋Z�p�I�ȗ͂́A�ЂƂ��Ɋ�̖��C���̉Ɉˑ����Ă���v�Ƃ������t�ɐG������A����ɏ��яG�Y�́u�l�X�Ȃ�ӏ��v�̈�߂������āA
�u�u�l�X�Ȃ�ӏ��v�̈�߂́A���ہA�q���̒m�o�ƂĂ����łɃR�[�h������Ă��܂� �Ă��邱�Ƃ��������Ă���B���C�Ȋ�Ƃ������̂����肤��Ƃ���A�����炻��́u�v�����ׂ����̂ł͂Ȃ��āA�t�Ɋl�������ׂ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�u�V�ˁv�Ƃ́A�ߋ��ցA�n���ւƑލs����˔\�ł͂Ȃ��A�����ցA�I���ւƑO�i����˔\�̂��Ƃł���B�O�i���ލs�̗l����тт�ꍇ������Ƃ��������̂��Ƃ��E�E�v
�i���S�j�Əq�ׂ�B
��X����������R�̂��Ƃ���ɂ��Ă���A�����Ď��o�Ƃ��ĉf��������ł���`�Ԃ�F�ʂ��A���͒����Ԃ����Č�V�I�Ɋw�K���������Ă����W�ς̌��ʂł����āA�Ȃɂ����܂�Ȃ���ɂ��ė^����ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�l�ނ̍ŏ��Ƀ��m�N���[���ŃX�^�[�g������X���A����ƕ����̌����ɂ����đQ���F�ʂ��l�����Ă����A�Ƃ������Ƃ��ǂ����ŕ���������ǁA����͒J��̘_�l�Ƌ��ɖ{����˂��Ă���Ǝv��ꂽ�B
�܂��A�l�͈ȑO�A��O�ɓW�J�����������i�F������ăJ���o�X�Ɏʂ����Ƃ��Ă�����̊����͂Ȃ��Ǝv���Ă����B������ʎ��Ƃ��Ă̕��i�������̕��i�ɏ���͂��͂Ȃ��̂��A�ƁB����͍��ł��M���Ă������Ƃ̂悤�Ɏv����B�����A�Ƃ͏]���Ďʂ���邱�Ƃł͂Ȃ��A�ڂ��D�����Ƃ̒��ɁA�\���Ƃ��Ă̊G��̈Ӗ������݂���Ǝv���Ă���B�����ɁA���l�Ɖ�X���݂̊�Ƃ��u�Ă��Ԉӎ��̍��ق�����̂��B�l���䩑R�Ɨ��������܂܂ł͍ς܂���Ȃ��B
�Ƃ���Łu���R�E�v���ɂ��Ėl��̊����͗L�蓾�Ȃ��B���������R�E�̉��b���V���Ȍ`�ԂƐF�ʂ�T��B���R�E�̑O�ɂ����Ėl��͏�Ɍ����ł��肽���B�����ȑԓx���ˏo����Ǝ��R�E�̃��b�Z�[�W���L���b�`�ł�������ɓM��Ă����B�������癗�ނ��O�ʂɏo�ĕ\���͐��サ�A�����Ă����B�������������Ȃ������̂��Ƃ�J��W��̕��ŕ⑫���Ă݂悤�B
�u�u�����v�͔ے肷�ׂ����ł͂Ȃ��A�ނ��둸�d���ׂ��u�`���v�ł���A�u���ȁv���J��Ԃ����p�̒��ɂ���傢�Ȃ�L������Y��Ă͂Ȃ�܂��B�v�i���T�j
������P�Ȃ�R�s�[�Ƒ����Ă��܂�����܂ł��B�����������߂ł͊��ɐ����Ă��܂����c�[�A���s������Ă��܂����͐ϕ������c����܂��B�����ł͂Ȃ��A�`���̒��ɂ���͂������瑤�Ɉ����邱�ƂŁA�V���Ȉ�s��lj��ł���Ƃ������ƁB
�����ŁA���́u�����v�Ƃ������Ƃ��A���R�E�ɉ�������Ă��镁�ՓI�ȃJ�^�`�̔����Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ����B�܂茻��G��̂Ȃ��ɁA�s�f�ɐV�����Ɍ������ĖҐi���邱�Ƃ����ł̓t�H���[�ł��Ȃ������������āA���̉����Ƃ������̂��A���R�E�ɕY���Ă��邠��`�ƐF�A���Ȃ킿��C�A�Ɖ��肵�Ă݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����B�X���甭�M���ꂽ�u���̂̂��v���A���邢�͓V��̎W�R��������A�v����Ɏ��R�E�̂ЂƂ̘ȗ����i�������`���K�R������̂��Ƃ����z����ӂ炸�Ɂj�A�D��B�`���s�ׂƂ������Ƃ͂��������ɂ߂Čl�I�ȗ���ɗ����Ă̌ǓƂȍ�Ƃł��낤�B�����Ɏ��鐸�_�Ƃ��Ă̍��g���́A���Ƃ��Ε�X���z���ĎR�ڂɗ������҂ɂ����A���݊������Ƃ�������Ă��Ȃ��B
��Ȃ��Ƃ́A���������s�ׂ�ʉ߂��u���́v�����ȑ��B���J��Ԃ��A�ϗe���Ă����A���̗l���������邱�Ƃł���A�u�ϗe�v�Ƃ������Ƃ�`�����Ƃ̏����ɐ����Ă݂邱�Ƃ��낤�B����́u�ق���т������A��������S�̂�g�ݒ������݁v�ł���u�����ȍ��قɖڂ��~�߁A�����������邽�߂ɋǏ��I�Ȕᔻ��ςݏd�˂邱�Ƃɂ���Ď���Ɋ���������ϗe�����Ă����헪�v�i���U�j�ł�����B���������A�Ђ��Ắu��Ɓv����u�����v�ɂ�����ԂɕY���Ă�����̂������o�����Ƃ��o������ꂵ�����A�፷���̌������ɗ��������u���فv�Ƃ������̂��m�F�o�������ɂ��������Ƃ͂Ȃ��B���Ղ�ʂ��Č������܂݂邱�ƁA���邢�͌ɗ����Ԃ邱�ƁB���Ƃ����̂��Ƃ��A���I�ȓ�l�̍�Ƃ���w�Ԃ��Ƃ��ł���B
�����F���ɂ�����c��ȓ��Ђ̑��B��p���u����̓y�W�v�i�����s���p�فA��\�N�H�j�ɏo�i�����u�n�̂������v�i�Ă����ߓ�����L���B�ۑ����S�{�j�����Ƃ��A�o�����Ă��邾���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ������ł���B�܂��͈ӎ��͌ڂ݂��Ă͂��Ȃ��B���̃u���b�N��ςݏd�˂āA���ʂƂ��Ĕ���L���ɂ܂ł���ԃC���X�^���[�V�����́A���m�̗̈�ł͂����d������Ȃ��̂��B�ނ��낻�����z���邱�ƂŁA����G�N�X�^�V�[���Ăъ�B�ނ̎����ɂ���ď��ڂ鐸�삪��������B���̜����̔g�ɂ��䂽���Ă��邱�Ƃ��A��Ԃւ̐Z�H�𑣂������ĕώ����Ă����P�̂̑��B��p�ł���B�u�v��ʉ߂��Ă����̏��ꂽ���_�Ɏ��邱�ƁB�����S�ʓI�ȕ��Չ��ɐ���ς���Ă��܂����̂ł��Ȃ��B�u�v�Ɓu���Ձv�̊Ԃ��s�������鎋���̗]�T�͎c����Ă���悤�����A���̗]�T����X�Ɂu��̋����v�����B
����l�̍�ƁA���������̈�A�̔��\������������Ƃ��f����B��\��N�ɍ��͖����Ȃ�������������p�قɏo�i��������ȍ�i�u�G�s�^�t�E�~����́v�B���a�l���[�g���]��A�����O���[�g���̗��̒Y�����ꂽ������O�ɂ��ė��ߑ��Ƌ��ɓf���o���ꂽ���̂́A���ɂ��āu���v�Ƃ������݂����n�߂�B�������l�Ƃ��Ă̖T��𗣂�Ă����A����肶���ƍ�i�����͂ށu��v�̒��ɗ��ߎ���A�u���v�͂��ɐ��E�̑��݂ƌ��f�Ƃ��Ă̐X���ɕ�����������킳���B����ƏĂ��ꂽ�؍ށA�����ɂ͕����Ƃ��Ă̌��f�i�A�S�A���A�_�f�Ɖj�����߂���B��������Ҍ��s�\�ȏ�Ԃ܂Ő[�߂�ꂽ�K�v�Œ���̎p�ł���A�����Ƀ~�j�}���E�A�[�g�̉e���͗�R�Ƃ��Ă��邪�A���ʂƂ��Ă�����������Ă���̂ł͂Ȃ��B���E�̑����͂����ɂ��Ă���̂��A�Ƃ������ՓI���i���̖����܂������i��i�j�ɋ��߁A�����ł������������I����˂��i�ނ����ɁA�ƌ������͋����I�����������邽�߂ɂ́A�K���Ȃ�Ƃ������݂ɓ˂����炴��Ȃ��B�u���O���ɑ��B���鎄�I�ȑz�O�Ƃ���������Ȃ������Ƃ̊Ԃ̗����ߍ��킹�邽�߂̋���̍�E�E�v�i���V�j�ƌ�鎩�ӎ��Ɏx�����A�����ɔh������_�C�i�~�Y����D���A�����ɂ��ĉ����Ƃ����I�ȃ��x���i������ȏo�����������j��ʉ߂��邱�ƂŁA���邢�͂����ɐ₦���߂��Ă������ƂŁA���߂ė���������������Ƃ��ł���B���̍�Ƃ͗D��ĐM���̒u����L���Ȑl�ԓI�c�ׂ��������Ă���悤���B
�����Ɖ����Ƃ��ɁA���́i���邢�͋�Ԃ̉����Ƃ��Ă̂���j�Ɋ֗^���Ă����Ƃ����グ�Ă��܂������A����͂��Ȃ������R�̂Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B����͌���G��ׂ̊��Ă��鍢��ȏ��t�Ǝ˂��Ă��邱�Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ𗹉������̂��A�����ĊG��ɒ��ނ��Ƃ��ǂ�ȈӖ��������Ă���̂��A���݂̖l�ɂ͖����ɓ�����m���Ȏ��M���Ȃ��B���ʉ�𒆐S�ɔ��\���Ă�����\�N�ȍ~�̖l�̍�i���ӂ��A�����������ɂ����ꕪ�������čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B
���N�����炵�炭�u�F��v�Ƃ����^�C�g���Ő��삵�Ă������A���̌��t���Y�ݏo�����������́u����v���炫�Ă���B�G�̋�Ƃ��������̎��A���邢�͂������甭�����邠���́u�C�v�̂��Ƃ����́B���W�b�N���z���āA�Ƃ������͂��̃p���_�C����g�ݒ������߂ɁA����������ĐF�ʂ̎�����Ƃ��Ă����ς��������B���̂��߂ɂ͂��Ȃ若�\�Ȃ܂łɌ������F�ʂ̍��g�����Ƃ�Ȃ��B
���Ċ|����ꂽ�L�����o�X��O�ɂ��Ďb���̋�z�ɒ^�����̂��A�����ނ�ɂ����������Ă����B���ɐ����ꂽ�`�Ԃ͕�������Ӗ��������Ȃ��B�g��U���̂Ȃ��ł������A�������V���Ȃ��̂������B�ꂵ�Ă���B�v���̂ق�����ȐF�ʁB���m�������̂��̂ĂĂ����E�C�������ƁA����͂܂�Ȃ̎��_�������B��ł���Ƃ������Ƃ��m���߂��Ƃł��������B��̍��Ղ���������݂̂ł͉����̂������Ȃ����A�V���Șg�g���l�@���邱�Ƃɍs���������Ƃ�����o���Ȃ��B������A�l�̊����Ɋ�Â����C�����[�W���j�X�e�B�b�N�ȐF�ʂ������Ă������͂����B
���I���@�ɂ���āA�ق�̋͂��Ȃ���ɂ���ĊG��͕ۂ���Ă���Ƃ�������B�Ⴆ�Ύw��Ǝ��ʂ̐��Z���`�̋������Ӗ�������͉̂����B�s�ׂ͂������@�v����茋�сA�A�d�B����B�Ȃ�����A���̎w���Â߂����邱�Ƃ��́A��̍s���܂܂ɌȂ�������邱�ƂŁA�^����ꂽ���ʂɎ��R������������̂��B���̂Ȃ�G��͏�ɗ���Ă�����̂����炾�B���オ����Ă���ȏ�A��X�̊��������̗���ɂ����č݂�킯�ŁA���Ȃ킿����̔��f������Ȃ��̂��A���ʂƂ��Ă̊G��̎����ł�����B����͐����̂��������鎞�ɐ������ꂽ�]�蕨���̂��̂ł���A�����ĕ��n�ł͂Ȃ��G���g���s�[�傳���邱�Ƃł�����B
����ɂ��Ă��L���Ɍ��т����`�Ԃ��h���X�e�B�b�N�ɔr�˂ł���͂��͂Ȃ��B�w��͎����Ɗ�����H�����Ԃł��낤�B�����������ĉߋ��̃X�e�B�^�X�������o�����Ƃ��Ȃ��B��Ȃ��Ƃ͖͕킩��n�܂������E�ɂ����āA�Đ��ł͂Ȃ��h���Ƃ��āA���K�ł͂Ȃ��s�t�Ƃ��ẴV�j�t�B�A���ɋ��߂Ă������Ƃ��A���ꂩ���ɉۂ���ꂽ��̕��@�Ƃ���Ȃ�A���̕ӂ���ύt��˂��������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�u�������ł��邱�Ɓv���肪����ɍ�����u�e�R�S�A�R�T�A�F��v�̘A��g���킹�ɂ��Ă����A�u��̍s���܂܁v�ł���u�]�蕨�v�ł��邽�߂ɁA�����ւ��������̂������A�Ȃ�Ƃ��������̖����ł��邱�Ƃ��B�͂ꑐ��}�A�n�[�P���ƃJ���r�i�����ăU�C���B�x���̂����Ă��L�����o�X�݂̂Ȃ炸�p�l����{�[�����ƁA�g�߂Ȃ��̂Ŏg������̂͂ǂ�ǂ�Ƃ����B�����Ƃ��Ă������Đ��������Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B���������Ă������������̎�荞�ݍ�Ƃ����邱�Ƃɂ���āA�킸���������������ꂩ�牽�����Ă����̂��Ƃ������W�������Ă����C������̂��B
�u�F��v�ɂ��ẴA�v���[�`�́A�ȑO�u�g�̘_�v�Ƒ肵�ĎG���������Ă����̂ł���������Ő������Ă��������B�_�Ƃ������̂��Ƃł͂Ȃ�����ǁA�g�̂ɂ܂�邱�Ƃ����Ƃ��āA���̎��͂Ɏ��͂���������悤�ɕ������݂���z�O���܂Ƃ߂����̂��B�Ⴆ�Ύ�̓����i�u���b�V���X�g���[�N�j�ɉ������ċz�́A�`���l�ƕ`�����x���̂Ƃ̋����ɂ���Č��肳��邾�낤���A��u�̖ڂ̓����₻�̎��̓��I���@�ɂ���Ă��ׂĂ��ς���Ă���ł��낤�B�ł͂���͍��X�ƕω�����_�̓�����A���ɗh���X�̏��𑨂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɁA���܂ł��肩�ɂ���Ȃ��㕨�Ȃ̂ł��낤���A�ƌ����Ƃ����ł��Ȃ��B��͂�U��~�낳�ꂽ�M�̍s�����͂�����̂��B�����ĐU��~�낳�ꂽ�M�Ղ����̌`�Ԃ��Ăэ��݁A�F��I�肷��B�����ł͍Ď����͗L�蓾�Ȃ��B�������u���ɂ��ďĂ��t��������݂̂̂��B
��Ȃ��Ƃ́A�g�̂������Ă���l�X�Ȋ튯�₻�̗v�f���א�ɂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A���肠�邢�͐g�̂Ƃ������̂���̘A���̂Ƃ��đ��݂��Ă���Ƃ������Ƃ�Y��Ȃ����Ƃ��B����Ƃ������Ƃ͂��Ȃ킿�A�]�ւ̎h���ł���A��ւ̔��˂��Ӗ�����B�����������Ƃ��l���Ă����ƁA�F�ʂƂ������̂��i�X�ƌ��t�ł����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�u���鉽���v�Ƃ������̈Ӗ��ł����Ȃ��Ƃ���ɁA���������A�C�}�C���Ɍ����킴��Ȃ��B�{���͂��̕ӂɐ^�����B����Ă���悤�ł�����̂��B
�F�ʂɊւ��邱�Ƃ�������Ă������A���N��ɉ��l�̍ʗщ�L�ŌW���J�Â������ɏo�i������i�̃^�C�g���ɂ��āA�������q�ׂĂ��������B�u�F��v�ɂ�����F�ʂւ̃A�v���[�`�Ƃ͕ʂɁA�^�C�g���ւ̑z��������Ȃ�ɂ������B�u�햌
�E �X����̒��߁v�u���肬���v�B��������s�s�Ƃ��̎��ӂɊւ��镗�i�Ƃ��Ă̌��t�ł���B�u���肬���v�Ƃ́u�؊݁v�u�R�v�����قǂ̈Ӗ��Ȃ̂����A�l�������Ō������������̂́u�Ƃ�����A�����ւ̂܂Ȃ����͎��B�ɁA�]���u�Ӗ��Ȃ����́v�ƍl�����Ă������̂������A���͂����Ƃ��L�`�ȈӖ����Y�o����ꏊ���Ƃ����v�l�̓]���𔗂�v�i���W�j�Ƃ������Ƃł���A���ǂƂ��ẴL�����o�X�̂�����Ƃނ����Ƃ̊W�i���햌�ɂ���ĉE�ƍ��ɐU�蕪�����邱�Ɓj����ʂ̒��ɐݒ肷�邱�ƂŁA�����������ɗV���Ă��݂��������̂����A���t���z������̕\���͂͂Ȃ������悤���B�F�ʂ̎��������邾���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B�����ɐV���Ȏd�|���A�V���ȕ\���̊g�傪�Ȃꂯ�Ȃ�Ȃ��B
�G��̃G�������g�̈�i�Ⴆ�ΐF�ʁj�����s���A�Ȃ��̂ɋߕt���Ă������Ƃɂ���āA�����ɉ������߂�̂��H���̎���͌�����p�ɂ����čA�ɓ˂��h���鏬���ł���B���Ƃ�����ȍ�i�u�p�Y�I�ɂ��Đ����Ȃ�l�v�i�o�[�l�b�g�E�j���[�}���j�����̉���z�N����悢�̂��B����Ƃ����̋�ԂɎ�荞�܂�Ă��鎖�������֍s�����ƂȂǂ���Ȃ��̂��H�����ł͂Ȃ��ł��낤�B�u�m���Ȍ����ł���ȏ�ɖ����ɂЂ炩�ꂽ���H�̗̈�ł����Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��邽�߁v�i���X�j�ł��邵�u����Ȃ銴�o�I�ȉ��I�v�f���A�\�w�̎��o�̔��I���̂��݂��Ď��I����ɂȂ�v�i��10�j�A���̂��Ƃ̎�����ڎw�����Ƃł����낤�B�����Ă��̎����̉ۂ͂ǂ��ł������̂��A����ɑ��鑦���͂������댯�ɉ߂���Ǝv����B���͌��t�ł͂Ȃ������܂ł��u�����ɂЂ炩�ꂽ���H�̗̈�v�Ƃ������Ƃ��m�F����ɗ��߂Ă����ׂ��ł���B
�����u���I����v�Ƃ͉����A�\�w�̎��o�̃��x�����čs�����Ƃ��ǂ��������Ƃ��w���̂��B���������u�\�w�v�Ƃ͉��Ȃ̂��B����́u������f�B�e�[�����ߏ�Ȍ��O���̂����ɂ�ꂪ���ɗ��������ł���O�ꂵ�ĕ����I�Ȋ��v�i��11�j�ł���u���������������l�Ȃ�Ӗ�����ꂪ���ɂ����������\��v�i��12�j���Ă��邾���Ȃ̂��B�����Ă��̑������ʂ����Ė{���Ɏ��o�̃��x�����Ă����̂��H�����������͑����ɉ߂��܂��B
�l�͈ȑO�A��������n�܂����G��s�ׂ��ǂ����ŃX�����Ɛ��_���ɎC��ς���Ă����A����������̂悤�ȋ@�\�̑��݂Ɍ˘f���Ă����B�J�^���V�X�ł͂Ȃ��A�ނ��냁�^�����t�H�[�[�Ƃł������ׂ����B���̕ϊ����u��ʉ߂��邱�ƂŊG��Ƃ����C����������蒆�ɂł���B�������̍\���ɉ����傫�ȋ\�Ԃ�����͂��܂����B��Ƃ��F�ʂ���גu�����ƂŁA����Ζ��p�̂��Ƃ��Z��̍��������𗧂��オ�点�Ă��܂��B�`���[�u����P��o�����G�̋�A��ӂɂ��č��M�ȊG��̐X��ł����ĂĂ��܂��B�ǂ����ɍI���Ȏd�|��������̂����A�������Ȑ���Ɏ�̓͂��Ȃ����ǂ����������܂ł��c���Ă���B�u�\�ԁv�łȂ���u�^�f�v�Ƃł������ׂ����B�܂��X�͏�Ɂu�^�f�v�ƈ�G�����̊W����茋�Ԃ��Ƃł������������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�����������ɂ��̂��ǂ��������G���V���Ȓn���ɗU���N���܂ł�����Ȃ�A�����āu���ǂ������v�Ƌ�������s���s���̂����ɁA���̏\�S����Ӗ����\�ł��邩������Ȃ��B
�ނ��늸�R�Ƃ��āu�\�w�v�̃��x���ɗ��܂邱�ƁB�u�\�w�v�̔w��ɉ���Ă��̐[�x���v�������Ƃ��Ă��A�������ꂽ���͂܂��\�w�ɉ߂��Ȃ��B�ƌ����Ď��H�̗̈悪�����ɂЂ炩��Ă��Ȃ���A������܂��NJ��ɒ������Ă��܂����낤�B�u�^�f�v��������ɐF�ʂ�����ɂނ��邱�ƁB�u���]�̃y�V�~�Y����_�o�̃I�v�e�B�~�Y���ւƕϗe������v�i�h�D���[�Y�j���Ƃ̂����ɁA�N�₩�Ȉ�̐������Ăэ��ނ��Ƃ��ł���i������������܂��s����������Ȃ����j�B���������������č����荇���͂��Ȃ��ْ��x��ۂ��A��ʓ��ŏI�������邱�Ƃ̂Ȃ��C���[�W�̉ʂĂȂ��g�U�ƁA���̒f�Ђ��W�ς����Ȃ���Ȃ�Ȃ��u���H�v�Ƃ����A����Α�������댯�ȃx�N�g����s�݂Ȃ��琧����p�������Ă������ƁB���������͋ƂɁA����̊G��̈�̕�������������Ă���B��l�N�ɓ����Ă���́u�\�w�c���v�͂��̂悤�ɂ��ĕ��サ���B
��
�G�悪�O�����̐��E����̃C�����[�W�����Ƃ��ĕ��ʂɒu��������Ƃ��ɋN�����a瀂́A�ߑ�G��̚���Ƃ��ė����[���X�E�h�j�́u�G��Ƃ͐��ƐF�̍\���ɂ����Ȃ��v�Ƃ������t�ɏے������̂����A����͊��x���̗h��߂������݂܂ŗ�����ł��鎖�����B�m���ɐ��ƐF�Ƃ����G�������g�Ȃ��ɉ����`�����Ƃ��ł��Ȃ����A���ƌ����č\����z�����Ƃ����ł��Ȃ��������B�Ȃ�Ή����\�z����̂��B�����Č����\������̂��F�ʂ��������A�Ƃł������Ă��������B�_���I�ȃA�v���[�`�̕��@�͑�R���邾�낤�B�����������͏��F����łɂȂ肻�����Ȃ��B�͂Ǝv�����炷���Ɠ����Ă����悤�ȑ��݂ł���A�`���̊m���͑������Ă����Y���ł����Ȃ��A����ȕ߂炦�ǂ���̂Ȃ����̂�v����Ɂu���p�v�Ɖ�X�͌ď̂��Ă���悤���B
�������炭�́u���v�Ƃ��Ă̌l�������Ƃ��āA���̑O�ƌ�ɋY���A�g���X�t�B�A�����߂���Ɗ���Ă���B����Ă�����̂��}�����܂ŁA䩔��Ƃ����ÈłɂƂ����Ȃ��Œ肷�ׂ������Ȃ��A����͂܂����������Ă����u���v�ɂ������Ă���e�[�[�ł���B�c���ꂽ����͐���ɂ����ĉ������ׂ��ł���A����ȏ�̌��t�͕��Q�ł������ꉽ��̎��v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�u���C���[�W�v�̂��Ƃ����̂�s�ݏo�Y����ɋ�ɑς��A�łтɌ��������݂Ƃ��Ă̍�Ƃ��邢�͂��̋��|����݉������A�Ƃ肠�����̓L�����o�X�Ɍ��������ƁB�������`�����Ƃɂ���ċ~������͔̂��X������̂ł����Ȃ��A�����̎����͋^�╄�̂܂܂Ȃ̂��B���̂��Ƃ����m�̏�őΛ�����B
�@������܂��\���҂Ƃ��Ă̏h�}�Ȃ̂ł��낤�B
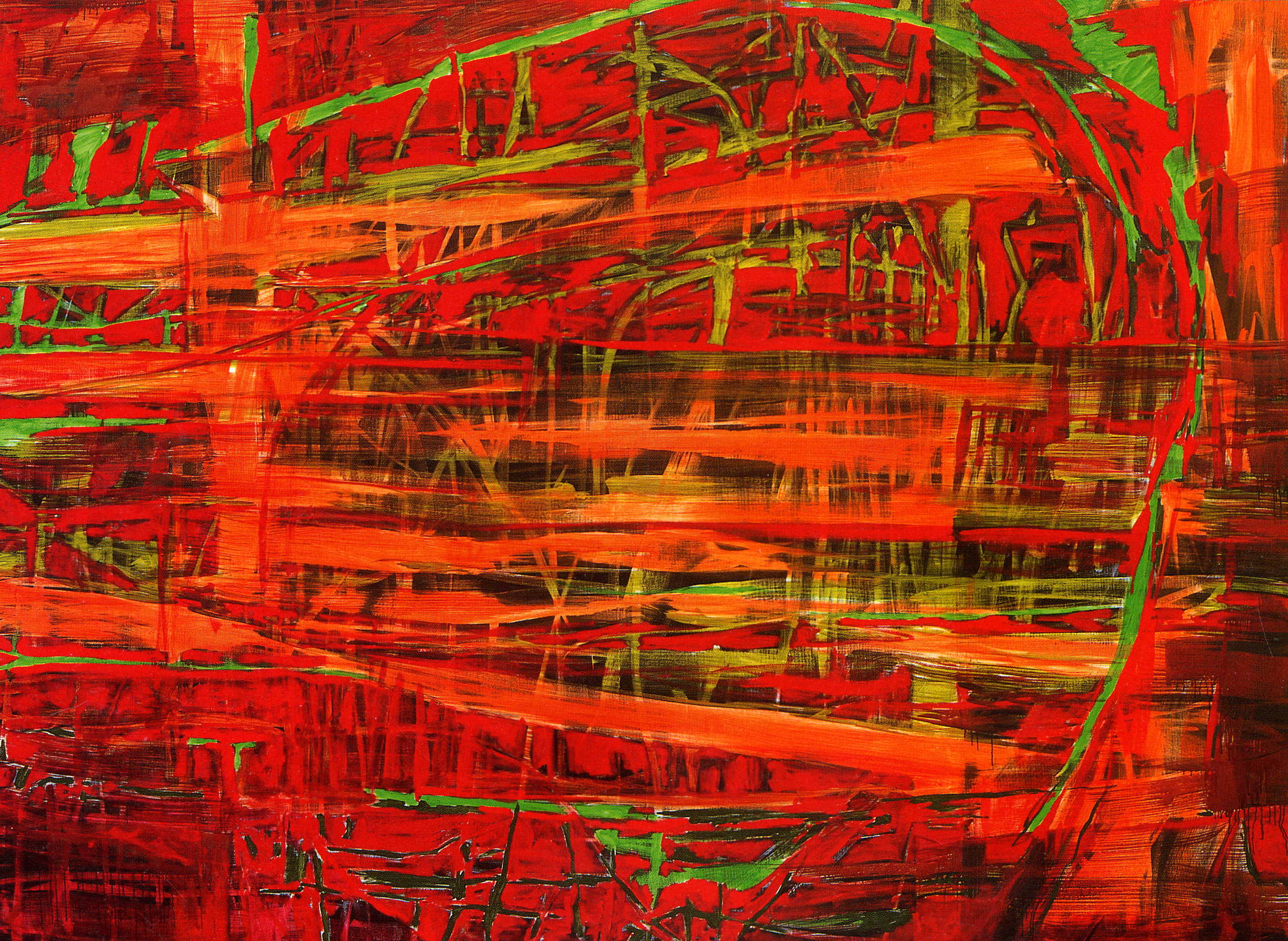 |
| ���������ʉ�u�\�w�c���E�S�O�v1995�N |
���P ���ܔN�ꌎ�ܓ��̓��L���
���Q �ΐ��k�u�M�I�̍\���v�������[
���R ��K�݂ǂ�u���b�g�E�C�b�g�E�r�[�v��w�̗F��
���S �J�숭�u�|�p���߂��錾�t�v�i���p�蒠�A��O�N�\�ꌎ���j���
���T �J��W��u�����V�����N��\�O���[���v���
���U ��c���u�ǔ��V����O�N�\�Z���[���v���
���V ���������u�G�s�^�t�E �����v�ܖ����@
���W �u����v�z�̃L�[���[�h�v�ʍ��B�Ȃ�����͑O�߂ł̕��J�s�l�̐��Ƌ��ʂ��� ���ł���B
���X ���؍_��u�_�b�Ȃ����E�̌|�p�Ɓv��g�o��
��10 �O�f��
��11 ��c���u�����_�v�����ܕ���
��12 �@���d�F�u�\�w��]�錾�v�����ܕ���
|